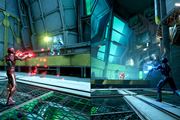2024年8月20日に「黒神話:悟空」が発売され、空前の悟空ブームが到来した。発売から2週間で、すでに全世界では1800万本を販売するなど驚異的な売上を見せている。数々の死にゲーをプレイしてきた筆者から見ても本作が本家フロム作品を除き、ソウルライクゲームの最高峰のひとつなのは間違いないように思う。そのくらい本作のゲームデザインは完成されている。
今回はそんな「黒神話:悟空」の魅力を、ストーリー全クリまでプレイした筆者の感想を基にレビューしていこう。
本作は中国のゲームスタジオ、GameScienceによって開発された西遊記の世界を舞台とするソウルライクゲーム。Unreal Engine 5をフルに生かした美麗なグラフィックで描かれる西遊記の世界と、主人公・悟空の棍による爽快かつ骨太なアクションが特徴だ。さまざまな敵を倒しながら待ち受けるボス戦に挑んでいくゲーム性や、隠されたアイテムなどを見つけていく探索性によってゲーム全体が構築されている。
だが、本作がもたらしたアプローチは既存のソウルライクゲームとは一線を画す、非常に独自性豊かなものであることがゲームを進めていく中ではっきりとわかった。ここからはいくつかの項目に分け、本作の魅力を掘り下げていこう。
本作のアクションの独自性は攻撃を重視したアグレッシブさにある。「ソウル」シリーズや「SEKIRO」でもそうだが、通常の死にゲーであればヒット&アウェイや防御・回避など敵の攻撃をかわす意識がバトルの基本となる。敵の攻撃に対して回避方法を見極め、パターンを予測することで隙を見つけ出し、的確なタイミングでダメージを与える。
スキルやアクションなどで違いは出てくるものの、既存の多くの死にゲーはこの基本に忠実だ。しかし、「黒神話:悟空」は通常の死にゲーであれば敵の動きに左右されて発生する隙を、プレイヤー自身が強制的に敵に押し付けるバトルデザインになっているのだ。
本作にはボタンによるガードやパリィが用意されておらず、敵の攻撃は基本的に”瞬身”という呼ばれるジャスト回避などのアクションでよけなければいけない。
本作のジャスト回避”瞬身”。敵の攻撃に対してタイミングよく〇ボタンを押すと悟空が残像を残しながら華麗に攻撃を回避する
本作の主人公である悟空は棍という武器を使用するのだが、攻撃は通常攻撃である”軽棍”(□ボタン)、強攻撃である”重棍”(△ボタン)に大きく分けられる。瞬身を成功させたり軽棍を当てたりすると”棍勢”というゲージが段階的に溜まっていき、それらを消費することで強力な技が繰り出せるというのが基本だ。
敵に通常攻撃である軽棍を当てると、画面右下の棍勢ゲージが溜まる
この”棍勢”を消費することで発動する攻撃に本作の真価が隠されている。軽棍で攻撃している最中に重棍を繰り出すと棍勢ゲージを1つ消費して”虚実撃”という一段階強い技が発生し、そこからさらに棍勢を消費すると大技の虚実撃を繰り出せる。ポイントは、2段階目の虚実撃がほぼ確実に敵を怯ませられることだ。
強力な虚実撃は半強制的に敵を怯ませられる。ちなみに△ボタン長押しで無理矢理棍勢ゲージを溜めても(蓄力)、大技が発動する
さらに1段階目の虚実撃を敵の攻撃にうまく被せると、ダメージを実質無効化しつつ2段階目の虚実撃につなげられるなど、プレイヤーのアクションスキルによってその強力さが増す。自分から仕掛けて敵の攻撃を無理矢理中断させ隙を押し付ける。この攻撃主義極まりないバトルデザインこそ本作の独自性の根幹である。
より強力な虚実撃、見切りの発動瞬間。敵からのダメージを無力化しより強力な2段目の虚実撃へと展開する
加えて、本作はスキルツリー要素も非常にうまく機能している。棍の振り方に3つの型(劈棍・立棍・刺棍)があり、それぞれのアクションの強化は基本的にすべてスキルツリーで管理されている。
劈棍は前方の小範囲に叩きつける技、立棍は棍を伸ばし広い範囲に攻撃を及ぼす技、刺棍は棍を前方に突き刺し距離をとった敵にも攻撃を当てる技が特徴。各型のスキルツリーを強化していくと、大技の虚実撃だけでなく、発動難易度こそ非常に高いものの、より強力な効果が付与された技も繰り出せるようになる。
本作のスキルツリー
面白い点は、このスキルツリーがすべて振り直しできることだ。たとえば、ひとつの型を極めたとしても、ボスによってはその型と相性が悪く、ほかの型を中心に戦ったほうが楽な場合がある。
そういった場合は、スキルポイントを振り直し、別の型の強化に変えると対処が楽になる。もちろん、型の強化以外にも、悟空自身のステータスの強化、術の強化などにポイントを振り直してもいい。
敵によって有効な戦法はさまざま。いろいろ試してみると攻略の糸口が見つかる
このスキルポイントの振り直しがほぼ必須であることが本作の秀逸な点だ。振り直し要素はほかのゲームに用意されていることがあるが、振り直しをしなくても敵を倒せる場合が多く、ほかのアクションに興味を持ったプレイヤーしか利用しないこともある。
しかし、本作はスキルツリーの振り直しをしないと勝てない敵が出てくるため、プレイヤーは状況によってスキルツリーの振り直しをせざるを得なくなる。その過程で自分がまだ試していなかったアクションや戦法を知れたりするため、これがプレイヤーの思考を刺激する大きな要素となっているのだ。本作はそのようなアクションゲーム的な面白さにプレイヤーを誘導するのにも成功している。
もうひとつ大きいのは術の存在だ。本作にはR2+各ボタンで発動するいくつかの術が用意されており、敵を強制的に停止させる定身術、悟空が残像だけを残し気体となって敵の視界から外れる気行術など、冒険を進めるほどに扱える術が増えていく。
本作の特徴をより生かしているのはやはり定身術で、使用すれば敵が止まっている間、一方的に攻撃できる。これを適切なタイミングで使えばプレイヤーがかけたい技を自由に繰り出せ、攻撃重視な本作のバトルデザインがよりプレイヤーに響きやすくなっている。
定身術発動中は敵の動きを無理矢理止め、好きな攻撃を叩き込める
本作の術は、このようにプレイヤーに敵に左右されない自由な時間を強制的に確保するものが多く、遊びやすさの一助となっている。
悟空がほかの存在に変身して攻撃する時間を作る変化や、道中で倒した敵を呼び出しサポートさせる魂魄など、棍以外の戦い方も実に多彩だ
本作では、先ほど述べた攻撃重視なゲーム性により、ボス戦が非常に盛り上がる。道中のボス数も非常に多く、フィールド内の少し強めの敵として登場する小ボスや中ボスもしっかり区別されている。
序盤でそこそこの強敵になる中ボス「白衣の秀士」。形態が2つ用意されており、HPを2回削りきらないと倒せない強敵だ
ボス戦では虚実撃や術を駆使して、徹底的に相手を怯ませハメ殺すようなアクションが求められるため、プレイヤーは積極的に攻撃を仕掛けていくのが望ましい。しかし、当然ながらボスの攻撃は強力なため、攻撃をはじき返され逆にこちらがピンチになってしまうこともある。やはり、ソウルライクとして最低限の慎重さや敵の動きを見極める意識はどのボス戦でも求められる。
しかし、そういった意識を徹底しなければボス戦は突破できないかと言われると必ずしもそうではない。むしろ逆で、大胆な動きこそが勝機につながる。これが本作ならではのボス戦の醍醐味だ。
たとえば、敵の攻撃に対して連続で瞬身が決まったり、強力な虚実撃をプレイヤーが狙わなくても偶然決まったりすることがある。こうなるとアドバンテージがとれるうえに、ボスのHPをかなり削ることも可能だ。
ボスであってもさまざまな技を組み合わせることによって、ほぼ一方的に攻撃を加えることも可能
このゲーム性によって、初見時はHPの半分くらいまでしか削れなかったボスが、何回か戦っていると途端に楽に倒せたりする。何度も死を繰り返すことで少しずつボス撃破に向かっていく一般的な死にゲーとは違い、プレイヤーの大胆な動きがふとしたタイミングでハマり、強敵の撃破まで持っていける。プレイヤーの直感的な操作が状況を打破するきっかけになるのだ。
ボス撃破の瞬間。演出も非常にカッコイイ
本作は通常の死にゲーとは違い、ロストシステムやデスペナルティが存在しないので死に対して慎重になりすぎる必要がない。果敢に攻撃を仕掛け、いかに相手に何もさせないかが重要なのだ。
ただし、直感的な操作で撃破できるのはあくまで道中に用意された小ボス、中ボスまでだ。章のラストに登場するボスはかなり強い。本作のアクションの特性を充分に理解していないと、大ボス戦で詰むこともある。
大ボスはHPが多く段階的に攻撃パターンを変えてくるうえに、喰らうと即死級の攻撃や、フィールドを生かした環境攻撃などを平気で使用してくるため、通常のボスとは比べ物にならないほど隙が作りにくいのだ。
大ボスとの戦いでもアクションがうまくハマるとなんとかあと少しというところまでくるのだが、たいがいのボスはこのタイミングで攻撃を激化し一気に戦いにくくなる。
劣勢に立たされると、回復薬が十分残っていても一回のミスで敗北まで持っていかれてしまうため、最後の数ミリはまさに命がけの攻防となるのだ。こちらから何とか隙を作りに行くしかなく、慎重にいきたい気持ちよりも時には意を決して敵と殴り合い、虚実撃を何が何でも叩き込む。このような立ち回りが求められる。
筆者が序盤に苦戦したボス妖王・黒熊怪。火による環境攻撃や、無敵時間、執拗な連続攻撃などが厄介で倒すのにほぼ一日を要した
装備やアイテムも最大まで強化し、その章で回れるところはすべて回り、術やスキルポイントの振り直しを極限まで活用しても倒しきれないほどの強さに設定されているため、ボスの撃破難度のバランスは本当に見事だ。やっとの思いで大ボスを倒したときの達成感は格別。ボスを撃破すると、奥ゆかしいアニメーションとともに次章へ進むことになる。
章末に意味深なアニメーションが流れるのも本作ならではの演出。過酷なボス戦終わりのちょっとした一息になる
最後に本作の世界観のすばらしさにも触れておこう。本作はフィールド探索をとおしてさまざまな西遊記の知られざる一面に触れられる。フィールドを進んでいると突如目の前に岸壁に掘られた大仏や、日本には存在しないほどの荘厳な仏閣、幾重にも立ち並んだ険しい山々など、古代中国ならではのロマンあふれる情景に出会えるのだ。Unreal Engine 5で造形された風景は、美しいこときわまりない。
西遊記の美しい情景の数々
そんな美しい風景の中で、ほとんどの日本人が知らないであろう西遊記の登場人物や逸話に出会える。古代中国の伝記ロマンに惹かれる瞬間が、本作にはいくつも宿っているのだ。
よく知られる西遊記の世界観をベースに持ちながら、制作陣のイメージする西遊記の世界に少しずつプレイヤーを引き込んでいくていねいさが感じられ、終始それがゲームの没入感に貢献していたと思う。
ゲームを進めていくと画像のような西遊記の美女も登場する
また、西遊記をダークファンタジー風に描こうとした作品が中国のスタジオから出てきた意味はかなり大きい。中国産のタイトルは数多くあるが、世界観や物語に関して独自性を備えるタイトルはあまり多くなかった印象だ。
しかし、西遊記という中国古来より知られている伝記を世界観に据え、中国だからこそ作れるゲーム世界を描いたのは非常に大きな意味を持つだろう。おとぎ話ではなく伝記としての西遊記を体験できるのは、本作ならではの魅力だ。
「黒神話:悟空」はゲーム業界の新たな勢力として急成長を遂げる中国のゲームスタジオの力強さをまざまざと感じられる傑作だ。Unreal Engine 5による圧倒的に美麗なグラフィックのゲームに留まらず、それらが強靭なアクションの描写力や、世界観に深みを与える情景描写などにも及んでおり、グラフィックがゲーム自体の面白さにも間違いなく貢献している。2024年を代表するゲームタイトルのひとつとなるのは間違いないだろう。