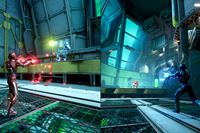カプコンの最新ゲーム「ドラゴンズドグマ 2」が2024年3月22日に発売された。本作のPS5版をやり込み要素も含めてストーリークリアまでプレイしたのでレビューしよう。なお、本記事ではストーリーに触れており、場合によってはネタバレに感じられる可能性があるので、その点だけ注意して読み進めていただきたい。
本作は、2012年にカプコンより発売された「ドラゴンズドグマ」の続編。前作はオープンワールド黎明期の国産オープンワールドゲームであり、その独自のゲーム性により多くのファンを獲得した。この最新作が12年ぶりに登場したというわけだ。
前作から4倍の広さになったフィールド、進化した物理演算で描かれるリアルな世界、多彩なジョブによる技やアクション、独自のAIで動く仲間、ポーンとの冒険などが特徴である。
次章からは、筆者なりに気になった点をピックアップして本作の魅力を掘り下げていこう。
本作のオープンワールドデザインは、一般的な現代ゲームのトレンドを考えるとかなり尖っていると言えるだろう。いわゆる、リアル志向のオープンワールドゲームであり、リアリティを高めるためにさまざまな制約的な要素が含まれている。そういったことから、ゲームを遊んでいて不便だと感じることが多々あるのだ。
たとえば、一般的なオープンワールドゲームでは当然実装されているファストトラベルが極端 に制限されていたり、キャラクターの荷物に重量制限が設けられていたり、食材系アイテムに 腐敗システムが実装されていたり、最近のゲームではなかなか珍しいゲーム要素が随所に散見される。
快適さを前提とする現代のオープンワールドゲームのトレンド、常識で見ると、本作はかなり前時代的なゲームに思えるだろう。
実際に本作の評価に関しては、その不便極まりないゲーム性が楽しめず、低評価を付ける意見も多く見られた。リアル志向のオープンワールドは、プレイヤーの好みによって評価が分かれるため、仕方ない部分があると思う。
しかし、さまざまなオープンワールドゲームを遊んできた筆者からすると、本作のオープンワールドデザインは決して古いものではないように思える。なぜかと言うと、ほかのリアル志向オープンワールドゲームでは、睡眠ゲージや空腹ゲージ、盗難システム、敵のロックオン機能非搭載など、リアリティを追及するための制約がもっと多いのだ。
そういったことを考えると、本作はリアル志向オープンワールドゲームの中ではかなり遊びやすいデザインと言える。
本作の尖ったオープンワールドデザインは、前作の仕様の多くをそのまま引き継いだことによるものだが、それらは制作サイドによる「ドラゴンズドグマ」という作品のコンセプトそのものを守るためのこだわりにほかならないだろう。
そして制作サイドがこだわりを貫いたことによって、本作はほかのゲームにはない独特で、かつ洗練された魅力が詰まったゲームだ。
本作の不便性を代表するシステムは、ファストトラベルの制限ではないかと思う。一般的なオープンワールドゲームと違い、本作のファストトラベルはいつでもどこでも自由に使用できるわけではない。ある程度自由なファストトラベルは、専用アイテム「刹那の飛石」を使用しマップ内の特定の場所「戻りの礎」まで瞬時に移動できる要素に限られる。
マップ内に点在する「戻りの礎」。「刹那の飛石」の効果でのみファストトラベルできる
ただし、「刹那の飛石」は発見機会がかなり限られているうえに、ショップでも数量限定、かつ高価な品なので大量に保有するのはかなり難しいアイテムだ。現実的に多用できるファストトラベル方法は街から街を移動できる牛車になる。
牛車は隣町同士を結ぶインフラ。街の停留所から乗車できる
牛車に乗っている間は時間をスキップすることができる。しかし、問題なのは、この牛車に乗っている間も敵と遭遇する可能性があることだ。敵と遭遇すると排除しない限り牛車が進まないだけではなく、牛車を破壊されると道半ばで放り出されることになり、そこからは徒歩で移動しなければいけない。
移動中に襲われる牛車。壊されると目的地までのファストトラベルは中断される
また、牛車はプレイヤーや仲間の攻撃でも壊れるため、戦い方を間違えるとみずから不遇な状況を呼び込んでしまう。この不便極まりないファストトラベルシステムも、一見すれば面倒なだけの要素だが、実はこういった部分にこそ本作の魅力が隠されている。
牛車が破壊された場合は、目的地まで徒歩で移動するのだが、その道中では以前通った場所でも新たなアイテムが見つかったり、洞窟や雑魚敵の溜まり場を発見したりする。ほかにも、以前倒せなくて逃げた敵と再び遭遇し、もう一度挑むと倒せるようになっていたりと、徒歩での移動を強いられる過程で、新たな発見やプレイヤーの成長が実感できる仕組みになっているのだ。
同じ道を何度も通ることで過去に逃げた強敵を倒せるようになっていることに気づいた瞬間は喜びもひとしお
これが「ドラゴンズドグマ 2」の本当に面白いところだ。ゲーム内に散りばめられた不便性がプレイヤーにとっての楽しい瞬間を不意に引き出す起点になっているのだ。
ほかにも、食べ物系アイテムが腐るという、一見不便なシステムにも奥深いゲーム性がある。食べ物系アイテムは「新鮮」「腐りかけ」「腐っている」の3段階で腐っていく。「腐っている」食べ物は、商品としての価値がなくなるだけでなく、食べると毒状態になってしまう。
ただし、「腐りかけ」状態まで熟成させると、より効能の高いアイテムに調合できるうえに、商品としての売値も上がる。「新鮮」の状態だと、調合してちょっとした回復アイテムにしかならない。
腐りかけの食べ物同士を調合して得られる「干し果物」や「干し芋」は、効能の高い丸薬の調合素材になる
つまり、「腐りかけ」まで待つと使い道が広がるが、うっかり熟成させすぎると腐らせてしまう、ちょっとした駆け引きがそこには存在するのだ。
さらに面白いのは、腐ってしまった食べ物にもちゃんと有用な使い道が用意されている点だ。腐った芋と肉は、互いに調合することでランタン用燃料になる。ランタンは夜間や洞窟を探索するのに必須のアイテムで、これがないと真っ暗でほぼ何も見えなくなる。
ランタンを使い続けるには、燃料を逐一補充する必要があるが、その際に腐った食べ物を用意しておくと、すぐに燃料を調合できるというわけだ。
腐った食べ物は、ランタン用オイルの調合素材になる。食べ物の腐敗システムにもきちんと意味があるのだ
一見使い道のなくなったアイテムが、特定の局面において超有用アイテムに変化する。こういった仕組みは、本作ならではの魅力だろう。
ゲーム内に用意された不便な要素や、一見面倒くさいシステムによってプレイヤーは通常のゲームでは起こりえない展開に巻き込まれるが、それゆえにゲームを進めていくうえで頭を働かせたり、工夫したりしなければならず、その先に意外な発見や成長に巡り合える。不便なシステムがもたらすランダムなゲーム要素、これこそが本作の本当に面白いところだ。
目的地までの道中で急に巨大な敵に瞬殺されてしまい、目的地までの別ルートを模索することになったとしても、その別ルートを通っているときに、新しいNPCから面白そうなクエストを受注できたりする。また、何度も同じ道を歩かされることが、単純にプレイヤーのレベルやジョブランクを上げることにつながっている。成長して新たな技を習得することで、それまでとはまったく違う戦闘を味わえたりする。
突如として街中に巨大な龍が出現する想定外の場面に遭遇することこそが本作の魅力だ
本作ならではの物理演算で支配された世界には、このような何が起こるかわからない、先の読めないゲーム展開が待ち受けており、それがプレイヤーの達成感や成長の実感につながる。何が起こるかわからないからこそ旅を進めるのが楽しみになる。この構造に気づけば、本作はいつまでも遊び続けてしまうゲームになるはずだ。
本作の面白さを語るうえでもうひとつ重要なのが仲間ポーンだ。仲間ポーンは、高度なAIが実装されており、シングルプレイゲームでありながら、友人と遊ぶオンラインRPGのようなゲーム体験が味わえる。
主人公となるキャラクター(覚者)と終始行動をともにする仲間メインポーンの2人をゲーム開始時にキャラメイクし、残り2人の仲間ポーンをリムストーンと呼ばれるポイントから呼び出せる。
仲間ポーンはマップに点在するリムストーンからいつでも雇える。道中に出会ったポーンを、お気に入り登録などで一時保存しておくことも可能だ
面白いのは、同じ仲間ポーンを使い続けるのが難しい仕様になっている点だ。主人公と仲間メインポーンは、道中の戦闘やクエストクリアをとおして成長していくが、借りてくる仲間ポーンは呼び出した時点からレベルが上がらない。そのため、敵が強くなってくると仲間ポーンを変えなければならないほか、蘇生不可能になった場合も新たな仲間ポーンを雇う必要がある。
仲間ポーンは、それぞれジョブや体格、性格が異なるため、組み合わせによって戦闘方法がその都度変わる。たとえば、主人公が回復役であるメイジを務め、ほかの仲間ポーンをすべて攻撃に特化させたジョブにすれば、ポーンたちが雑魚敵との戦闘を一瞬で終わらせてくれる。
ほかにも、巨大な敵に対しては、敵の体にしがみついて頭を直接剣で攻撃したり、敵がふらついた瞬間に足を重点的に攻撃することでダウンをとったりして戦うのがセオリーだが、仲間ポーンにソーサラージョブがいれば、大ボスでも魔法で一気に敵の体力を削って倒せるのだ。
このように、仲間ポーンのジョブの組み合わせで戦闘方法が変わるため、ポーンを変えるたびに新たな戦い方の発見がある。これが本作の面白いポイントだ。
加えて、仲間ポーンは、それぞれで性格が異なるため、同じジョブでも行動が変わる。主人公の回復や、前線での攻防など、ポーンの性格によって優先する行動が違うので、これによっても戦闘などの方法が変わってくる。
仲間ポーンと歩む道中は、それ自体にも本作ならではの魅力が詰まっている。ポーンは自身が異界(ほかのプレイヤーの世界)で見てきた宝箱や重要ポイントの場所を覚えており、その場所に近づくと方向を示してくれるのだ。
仲間ポーンに付いていった先で思わぬ強敵と遭遇してしまったり、逆にレアアイテムを見つけたりなど、仲間ポーンを信じるか、それとも自分で行き先を決めるかも、プレイヤーの選択次第というわけだ。
仲間ポーンは道中にたわいもない会話を続けており、和気あいあいとした旅路を演出してくれるほか、プレイヤーのことを「覚者様」と呼んで常に慕ってくれるため、仲間ポーンとの冒険自体が面白くなってくる。戦闘が終わったら仲間ポーンとハイタッチし、暗くなる前に一緒にキャンプをする。こういった心地いい冒険も本作ならではの魅力だろう。
酒場では仲間ポーンと飲み会を開くことも可能だ
仲間ポーンとは関係ないが、キャンプで料理すると、なぜか実写の肉の映像が流れる。おいしそうだが、シュールだ
「ドラゴンズドグマ 2」は、不便なゲーム性をあえて前作から継承させ、プレイヤーの思考や工夫をうながし、予定調和の範疇に留まらない独自のゲーム性を確立している。プレイするほどに完成度の高さを感じられるだろう。
確かに、癖の強いオープンワールドゲームに変わりはない。また、前作を長時間プレイしたユーザーだと新鮮さに少々欠けると感じるかもしれない。しかし、「ドラゴンズドグマ」本来の魅力をより洗練された形で継承した本作には、ほかのゲームにはない面白さがある。こういったゲーム性に興味がある人は、ぜひ一度遊んでみてはいかがだろうか。