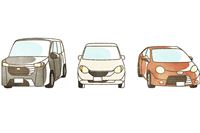前回の記事「軽自動車VSコンパクトカー! あなたならどっちを選ぶ?(そもそもの両者の定義と経済性比較)」では主として経済性の面から軽自動車とコンパクトカーを比較してきましたが、当然ながら結果は軽自動車の圧倒的優勢といったところです。ここからは運動性能など自動車としての商品性そのものを、引き続き元モーターマガジン誌の矢部亨氏に比較してもらいます。(編集部)
街中の込み入った細い路地を走るときなどにいかに運転しやすいかを表すのが、この取り回し性。近い言葉で言えば、「小回りが利くか利かないか」になるだろうか。
取り回しの良し悪しは、実際にその車に乗って狭い路地を走ってみるのがいちばんよくわかるが、カタログのスペックからもある程度は類推できる。
簡単に言えばボディサイズの小さな車ほど取り回しがよくなる。スペックとしては、全長、全幅、全高、ホイールベース (前輪軸と後輪軸の距離)、トレッド (左右のタイヤの接地面の中心間の距離)、最小回転半径が短いほど基本的には取り回しはよくなる。実際にはこれらのスペックに加えて、ハンドルの切れ角やボディの見切りのよさ(視界)などの要素も加わってくる。
ボディサイズというとまず全長×全幅×全高を思い浮かべるが、そのほかのサイズ的なスペックもすべてそれに比例するかというと、実はそうでもない。
軽自動車は、限られた規格の中でなるべく室内空間を大きく取ろうとする傾向が特に強い。そのためにタイヤをなるべく隅に置いている。
同じホンダで軽自動車の「N-WGN」とコンパクトカーの「フィット」を比べてみよう。両車ベーシックグレードのFFモデルだ。
ホンダの軽自動車「N-WGN」
ホンダのコンパクトカー「フィット」
全長はフィットのほうが60cm長いが、ホイールベースはその差10cmに縮まる。全幅も「フィット」が「N-WGN」より22cm広いが、トレッドは前18cm/後17cmとその差は縮まる。
そうした差の集積としての最小回転半径となると、「フィット」の4.9mに対し「N-WGN」は4.5m。ほかのモデルを見ても、軽自動車の最小回転半径が4.4m前後なのに対し、コンパクトカーは4.9m前後。
さらに軽自動車は、ボディ自体が小さいことに加え、特にトールワゴンタイプでは視座が高くなるので、その分見切り=視界もよくなる。
取り回しに関しては軽自動車が優位と言えそうだ。
室内空間の広さについては、道路運送車両法で一回り大きなボディサイズを認められているコンパクトカーの優位は否めないだろう。前述のとおり、軽自動車はタイヤの配置を工夫するなどして、居住空間をめいっぱい広く取ってはいるが、室内高(全高に関する道路運送車両法の規格は両車2mで同じ)以外はコンパクトカーを逆転するのはかなり難しい。
室内高を高く取る軽自動車が多いのは、乗員を立ち気味に座らせて前後方向の専有面積を減らすことにより、居住性を高めようという考え方による。
スズキ「エブリイワゴン」などの1BOXを除いた主な軽自動車の室内寸法は、室内長:2,055〜2,450mm程度/室内幅:1,345〜1,355mm程度/室内高:1,300〜1,420mm程度。
いちばん小さな軽自動車、ダイハツ「ミライース」
で室内長:1,935〜2,025mm/室内幅:1,345mm/室内高:1,240mmだ。
ダイハツの軽自動車「ミライース」の室内
ダイハツの軽自動車「ミライース」の室内2
いっぽう、最量販コンパクトカー、トヨタ「ヤリス(1.0X)」を例にとると、室内長:1,845mm/室内幅:1,430mm/室内高:1,190mmと、室内幅以外は一般的な軽自動車より小さい。
トヨタ「ヤリス」の室内
前述のホンダ車同士でも「フィット」は軽自動車の「N-WGN」より室内長で10cm、室内高で4cm短い。室内長の逆転に関しては、軽自動車が荷室を犠牲にしてでもキャビンを広く取ろうとするのに対し、コンパクトカーはある程度の荷室容量も求められるという事情もあるが、室内長の測り方による部分が大きい。
室内長とは、車両中央部でインパネの最も出っ張った部分の先端から後部席シートバック後端までの長さを測ったものなので、荷室部分の長さは含まれない。事実上居室に限ったスペックと考えたほうがよい。
荷室も含めた室内空間となるとやはり、多くのモデルが実用的にも必要充分なスペースを確保しているコンパクトカーに軍配が上がるだろう。
軽自動車の室内空間について、実際に乗っていて特に気になるのが室内幅。運転席/助手席に2人で並んで座ると、特に体格の大きな男同士の場合など、余計に間隔が狭く感じられる。
これも「フィット」と「N-WGN」の例で言うと、ボディ全幅差は22cmあるが室内幅は縮まってフィットが9.5cm広いだけになる。だが、この差は実際は数値以上に大きく感じるはずだ。
自動車に基本的に求められる機能は、「走る」「曲がる」「止まる」で、これを走行性能と言う。シャシーから始まり、エンジンやモーターなどのパワーユニット、ミッション、サスペンション、ブレーキシステム、タイヤに至るまで数多くの部品、メカニズムの組み合わせや技術の総合力とも言える。
日本の自動車メーカーは規模の大小こそあれ、そこから産み出される製品=自動車について、これらの性能が「低い」という評価を与えられることはまずないと言ってよい。
そんな中で、軽自動車VSコンパクトカーという図式で見れば、たとえば「(速く)走る」という点では同じガソリンエンジン車同士で比べれば、排気量の大きいコンパクトカーが有利なのは確か。
単純に言えば、高速道路を同じ速度で走る場合(軽自動車の制限速度は80km/hだが)、普通は軽自動車よりコンパクトカーのほうがエンジン回転数は低くて済むので、静粛性は高くなる。静粛性は乗り心地や疲労度にも影響してくることが多い。
加えて、コンパクトカーのほうが車体が大きい分、また、軽自動車よりも高い車両価格を設定できる分、遮音対策を施しやすいので、この点でも静粛性は上がるだろう。
また高速道路では、トールワゴンタイプの軽自動車は全高が高い分、車体側面の面積が広くなるので、横風にあおられやすくはなる。
さらに、全高が高いと重心も高くなるので、「曲がる」際に不安定感を覚える人もいるかもしれない。
「止まる」については、概して車重が軽いほうが制動距離は短くなる。2022年の国土交通省の統計によれば、車両重量の中間平均値は、軽乗用車が891kg、普通・小型乗用車は1,526kgと、軽自動車は普通自動車の6割程度。
「止まる」に関しては、軽自動車が有利と言えそうだが、そのほかの走行性能/乗り心地全般はコンパクトカー優位と言えそうだ。
現在、どの自動車メーカーもいちばん多くの開発費をかけているのが環境性能と安全性能だろう。自動運転技術も大きく言えば安全性能のひとつと言える。
安全性能に関しては、道路運送車両法や税金のように軽自動車独自の基準があるわけではなく、性能試験の内容も基本的にコンパクトカーと同じだ。
国交省と独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)は一体となって毎年いろいろな車の試験を行っており、その結果はJNCAP(自動車アセスメント)としてネットでも公開されている。
JNCAPは、事故を未然に防ぐ予防安全性能と、衝突してしまったときにどれだけ乗員の安全を確保できるかという衝突安全性能などによって評価される。
2023年度版の衝突安全性能の評価点を見てみると、中にはコンパクトカーと比べてもまったく見劣りしない高い安全性能を持つ軽自動車もある。
そのため、単純に軽自動車全般対コンパクトカー全般という比べ方はしづらい面もあるが、衝突安全性に大きく影響する「クラッシャブルゾーン」だけを取り上げると、一般論として言えることはある。
クラッシャブルゾーンとは、衝突時に乗員の損傷を最小化するために、ボディをやわらかい部分と丈夫な部分に作り分け、やわらかい部分を敢えて潰して(クラッシュさせて)衝撃を吸収し、頑丈に作ったキャビン内の乗員の安全を図ろうという考え方だ。
現在はほとんどの車がモノコックフレーム(車体に独立した骨組みを持たせず、ボディ外板そのものに骨組みの役割も兼ねさせて全体の強度を出す構造)だが、このモノコックフレーム自体の鋼材も潰す部分と丈夫な部分では違うものを用いたりする。
で、どこがクラッシャブルゾーンなのかというと、3BOXセダンを思い浮かべるとわかりやすい。
前のBOXがやわらかい構造のエンジンルーム、真ん中のBOXが頑丈に作ったキャビン、後のBOXがやわらかい構造のトランクルーム。前突時はエンジンルームを、後突時はトランクルームを潰すことで衝撃を吸収し、丈夫に作ったキャビンを温存しようというわけだ。
だが、コンパクトカー、軽自動車問わず、エンジンルームと独立したトランクルームの両方を持つモデルは、2シーター・オープンカーのダイハツ「コペン」くらいしか見当たらない。
このクラスでは珍しいエンジンルームとトランクルーム構造を持つダイハツコペンは、「骨格+樹脂外板」と車体の構造もやや異なる
ダイハツ「コペン」試験車両の55km/h後面衝突実験
ほとんどのコンパクトカーは2BOXのハッチバック車で、エンジンルームはあるが独立したトランクルームはない。
だが、前突時はエンジンルームがクラッシャブルゾーンになるし、後突時もトランクルームはないものの、それなりの荷室長があるので、そこがクラッシャブルゾーンになる。
トヨタのコンパクトカー「ヤリス」の構造図
いっぽう、ほとんどの軽自動車は室内空間をできるかぎり広く取るためにトールワゴンとなっている。BOXという言い方では2BOXのハッチバック車となるが、エンジンルームはBOXとして数えるほどの前後長はないので、1.5BOXと呼んだりもする。
荷室長も居住空間確保のためにコンパクトカーほどは取っていない。
同社が「G-CON」と呼ぶ衝突安全技術を投入するホンダ「N-BOX」のストラクチャー、各社が限られたスペースの中で予防安全機能等も組み合わせて安全性を競う。
少なくともクラッシャブルゾーンを大きく取るという点に関しては、ボディサイズが大きい分コンパクトカーのほうが有利なようだ。
ここまで軽自動車とコンパクトカーを総論的に比較してきた。この人にはこちらがおすすめという言い方はできても、総合的にどちらがすぐれているというような結論は出ないだろう。
だが、いちばん近いカテゴリー同士のこの2車、一長一短ありつつ、同じ土俵にのせて比べて無理はないはず。
実際に購入する際は、安さだけで選ぶのではなく、逆に高いからと言って敬遠するのでもなく、諸性能、車型、車体サイズ等々自分の乗り方や目的にかなったモデル選びをしていただければと思う。
(次回以降は、シチュエーション別の軽自動車、コンパクトカー、おススメ、イチ押し検討を試みます)