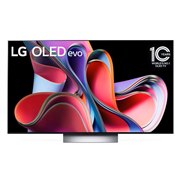2022�N���f�������グ�čD�]������42V�^�L�@EL�e���r4�@���r���r���[�ɑ����A2023�N�͐l�C�̍����T�C�Y�ł���55V�^�L�@EL�e���r5�@���r���r���[�����{�B
�l�C�̍����T�C�Y�тƂ��������łȂ��A�e�Ђ̍ŐV�Z�p���������ꂽ�n�C�O���[�h���f�����W�܂��Ă���B���������e�Ђ̗L�@EL�e���r�������тŔ�r����@��͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��̂ŁA�M�҂Ƃ��Ă������ÁX�̎�ނƂȂ����B �������A������掿�̈Ⴂ�͈ȉ��̓���Ŋm�F�ł���B���ЁA4K/60p�ōĐ����Ă݂Ăق����B
��ނ��s�����̂́A�u���i.com���炵���{�v�B��ʓI�ȃ}���V�����̈ꎺ�ł͂��邪�A���r���O���[���̃X�y�[�X���L���̂ŁA55V�^�e���r��5����ׂ邱�Ƃ��\���B
��r�����͊�{�I�ɑO��Ɠ��l�ŁA�u���[���C���R�[�_�[�̃p�i�\�j�b�N�uDMR-ZR1�v���v���[���[�Ƃ��Ďg�p�B���̏o�͂��G�C���d�q��4K/60p�Ή�HDMI�X�v���b�^�[�uAVS2-18G108�v���g����5��ɕ����A���ׂĂ��ɐڑ����Ă���BHDMI�P�[�u�������ׂē������̂ő�����ȂǁA�\�Ȍ��蓯�������Ƃ��Ă���͍̂�N�Ɠ��l���B
�e�X�g�@��5�@��B������A�\�j�[�uXRJ-55A95K�v�A�V���[�v�u4T-C55FS1�v�ALG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�A�p�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v�ATVS REGZA�u55X9900M�v
�Đ��\�[�X�͊�{�I��Ultra HD�u���[���C�B�X�v���b�^�[���g���s���ŁA���ׂ�HDR10�Ƃ��čĐ����Ă���
�v���[���[�Ƃ��Ďg�����̂̓p�i�\�j�b�N�́uDMR-ZR1�v
�uDMR-ZR1�v����o�͂����f���M�����G�C���d�q�̃X�v���b�^�[�uAVS2-18G108�v�ŕ���B5�䓯���ɓ����f�����f���Ď������s����
2023�N���f���̗L�@EL�e���r���r���[�ł̃|�C���g�́A����p�l���̈Ⴂ���B��^�L�@EL�e���r�̃p�l���Ƃ����A�o�ꏉ����LG�f�B�X�v���C��WRGB�^�C�v�̃p�l���݂̂������B���[�J�[�ɂ���ăp�l���̐���ɂ�鍷�����������Ƃ͂��������A��{�I�ɂ͂ǂ��̃��[�J�[���p�l�����͓̂���LG�f�B�X�v���C���������̂��B
�������A�ŋ߂ł͏��قȂ��Ă��Ă���B�T���X���f�B�X�v���C���uQD-OLED�v�Ƃ����V�����e���r�����L�@EL�p�l�������p�����A���{�����ł�2022�N�Ƀ\�j�[���L�@EL�e���r�ɍ̗p�����̂��B�uQD-OLED�v�̓p�l�����̂̔����F�͐F�ŗʎq�h�b�g�V�[�g�߂��邱�Ƃŏ��x�̍����F�����o����B�e�F�̐F���x�����������łȂ����P�x�������ł���Ƃ������́B
�E���T���X���f�B�X�v���C���uQD-OLED�v�p�l���̃C���[�W�B����LG�f�B�X�v���C���p�l���̃C���[�W�BWRGB�����ƌĂ�邱�Ƃ�����
LG�f�B�X�v���C��WRGB�^�C�v�͍��P�x���̂��߂ɐԁ^�^��3���F�ɔ���������4�F�ŕ\������i�����F���͔̂��j�B�J���[�t�B���^�[�ɂ����RGB�̌������o���Ă���Ƃ������Ƃ��B������������ɍ��P�x����i�߂Ă����o�܂����邪�A2023�N�͏�ʂ̑��݂Ƃ��āuMLA�i�}�C�N�������Y�A���C�j�v���̗p�����p�l�����o�ꂵ���B����͔����ȃ����Y��z�ăp�l�����琶��������W�߂Č����ǂ��Ǝ˂��邽�߂̂��̂ŁALG�f�B�X�v���C�ł́uMLA�v���g�����Z�p���uMETA�e�N�m���W�[�v�ƌĂ�ł���B
�Ȃ��A�uMLA�v�p�l�����̗p�����p�i�\�j�b�N��2023�N���f���uMZ2500�v�V���[�Y�́A2022�N�̃r�G���X�^���_�[�h�L�@EL�e���r�uLZ1800�v�V���[�Y��i55V�^���f���u55LZ1800�v�j�Ŗ�2�{�̍��P�x����B�����Ă���Ƃ����B
�uMLA�v�ł́A�]���͓������˂ɂ���Ăނ��ɂȂ��Ă����������܂����o���A��������}��B���̃����Y����77V�^��424����
LG�f�B�X�v���C�ł́uMLA�v���̗p�����Z�p���uMETA�e�N�m���W�[�v�Ə̂��Ă���B���̂��߁A���̃p�l���́uMLA�p�l���v��uMETA�p�l���v�ƌĂ�邱�Ƃ�����
���̂悤�ɗL�@EL�p�l���͑傫��������2��ނɂȂ����킯�ŁA�e�Ђō̗p���Ă���p�l�����قȂ��Ă��邱�Ƃɒ��ڂ������B
���������L�@EL�e���r�ł́ALG�G���N�g���j�N�X�ƃp�i�\�j�b�N�́uMLA�v���ڂ�WRGB�����A�V���[�v��2023�N�d�l�̍ŐV�uQD-OLED�v�A�\�j�[��2022�N���f���̌p���̔��Ȃ̂�2022�N�d�l�́uQD-OLED�v�A���O�U�́gMLA�Z�p�𓋍ڂ��Ȃ��h2023�N�d�l��WRGB�����ƁA�����p�l�����g���Ă���̂�LG�G���N�g���j�N�X�ƃp�i�\�j�b�N�����ŁA�ق��̓p�l�������̗p�Z�p���قȂ���̂ƂȂ��Ă���B
����܂ł������L�@EL�p�l�����g���Ă����Ƃ��Ă��A�e�ЗL�@EL�e���r�̉掿�͈قȂ��Ă����B����̓e���r�̂��߂̉��肪���[�J�[���ƂɈقȂ邽�߂����A���N�̓p�l�����̂ɂ��Ⴂ���o�Ă��Ċe�Ђ̉掿�̈Ⴂ������ɑ傫���Ȃ����B������̃|�C���g�̓p�l���̍��P�x���ɂ���ʂ̖��邳�̈Ⴂ���B
���悩���o�����e�ЗL�@EL�e���r�̉掿�̈Ⴂ�B�掿���[�h�́u�I�[�g�v��u�����v�������́u�W���v�ɏ��������́B���̎ʐ^�����������ł��A���ꂼ��̉f���̈Ⴂ���킩���Ă��������邾�낤
5�@���2023�N12��25�����_�ł̉��i.com�̍ň����i�͎ʐ^�̂Ƃ���B�e�Ђ̃n�C�G���h���f���Ƃ����Ă����i�ɍ������邱�Ƃ͗��ӂ�����
�uTH-55MZ2500�v�́uMLA�v���ڂ�WRGB�����p�l�����̗p�B�p�l���̔w�ʂɂ͓Ǝ��v�ɂ��o�b�N�J�o�[��̌^���M�v���[�g�ƓƎ��f�ނ̕��M�V�[�g�Ȃǂ�lj����ăp�l�����\�������o���Ă���B�f�������G���W���́u�w�L�T�N���}�h���C�u �v���X�v�ŗL�@EL�p�l�������ɍ��킹�ĐF���A�Õ��▾���ł̊K���ƐF�Č��������x�ɍs���B�X�s�[�J�[�͉�ʉ��ɏ��^���j�b�g�����ׂ����C���A���C�X�s�[�J�[�����C���Ƃ��A���ʂ̃��C�h�X�s�[�J�[�Ə㕔�̃C�l�[�u���h�X�s�[�J�[���B�w�ʂɂ̓E�[�n�[�ƃp�b�V�u���W�G�[�^�[�������A�����ꂽ�T���E���h�Đ����������Ă���B
�uOLED55G3PJA�v�́A�uMLA�v���ڂ�WRGB�����p�l�����̗p�B�f�������G���W���ɂ́u��9 AI Processor 4K Gen6�v���̗p���AAI�Z�p�ɂ���Ď�������ԑg�ɍ��킹�čœK�ȉf���Ɏ����Œ�������@�\��������B�����X�s�[�J�[��4.2ch�\���ŁADolby Atmos�ɑΉ����ăo�[�`����9.1.2ch�̃T���E���h�@�\��������B�w�ʂɉ��ʂ̂Ȃ��t���b�g�Ȉꖇ�f�U�C�����̗p���Ă���f�U�C�����ɂ��������B�܂��A��p�̕NJ|��������g�p���邱�Ƃŕǂɂ҂�����Ɗ��NJ|�����\���B
�u4T-C55FS1�v�́A�T���X���f�B�X�v���C��2023�N�d�l�uQD-OLED�v�p�l�����̗p�B�Ǝ��̕��M�\��������āA���P�x�����łȂ����ψꐫ�̌���Ȃǂ��ʂ����Ă���B�f�������G���W���́uMedalist S4X�v�𓋍ځBAI�ɂ���ĉ掿��������������uAI�I�[�g�v���[�h�������B��������X�s�[�J�[�́uARSS+�v�Ƃ������̂ŁADolby Atmos�Ή��B��ʉ����̃t�����g�X�s�[�J�[�̓`�����l��������~�b�h�����W�~2�ƃc�C�[�^�[�~1��3���j�b�g�A��ʏ㕔�̃n�C�g�X�s�[�J�[�̓~�b�h�����W�{�c�C�[�^�[�Ƃ���2���j�b�g�\���B����ɔw�ʂɃT�u�E�[�n�[������邽�߁A���v���j�b�g����11�ɂ��̂ڂ�BOS�́uGoogle TV�v�ŁA�e���r�^��⓮��z�M�T�[�r�X�ւ̑Ή������S���B
���ʐ^��65V�^
�uXRJ-55A95K�v���T���X���f�B�X�v���C�́uQD-OLED�v�p�l�����̗p���邪�A��N����̌p���̔����f���̂��߃p�l����2022�N�d�l�B�f�������G���W���͔F�m�����v���Z�b�T�[�uXR�v���BOS�́uGoogle TV�v�ŁA�Ǝ��̓���z�M�T�[�r�X�ł���uBRAVIA CORE�v��������B�X�s�[�J�[�͉�ʂ�U�������ĉ����o����^�A�N�`���G�[�^�[�Ɣw�ʂ̃T�u�E�[�n�[2�@�ɂ��u�A�R�[�X�e�B�b�N �T�[�t�F�X �I�[�f�B�I�{�v�B�������Dolby Atmos�ɑΉ�����B2022�N����̌p���̔��Ƃ͂Ȃ���̂́A�ŏ�ʃ��f��������{�I�ȋ@�\�ł͑��Ђɑ��Ă���F�͂Ȃ��B
�u55X9900M�v�́gMLA�𓋍ڂ��Ȃ��h�ʏ�^�C�v��WRGB�����̃p�l�����̗p�B�f�������G���W���́u���O�U�G���W��ZR���v��AI�Z�p�����p�������X�̍��掿�E�������Z�p���̗p���Ă���B����Ƀ~���g���[�_�[��������Ď�������l�̈ʒu�⋗����c���A���̈ʒu�ɍ��킹�čœK�ȉ掿�E�����֍œK������Z�p��������B�X�s�[�J�[�́A��ʂ̏㉺���E�A��ʂ�U�������ĉ����o���A�N�`���G�[�^�[�A�����Ĕw�ʂ̃T�u�E�[�n�[���v10�̃��j�b�g�ɂ��u�d�ቹ���̉����V�X�e��XHR�v�B�����Ēn��g������6�`�����l���܂œ����ɘ^��ł���u�^�C���V�t�g�}�V���v�𓋍ځi�O�t��USB HDD�̑��݂��K�v�j�B��v�ȃe���r������^��\��Ȃ��Ŏ��R�Ɋy���߂�@�\�����B�掿�E������������邪�A�����͂̍��������͂��B
�ł͎����ɓ��낤�B�܂��͖��邢���ł̎������B�e�X�g���s�����u���i.com���炵���{�v�͊O�������閾�邢�����ŁA����Ɏ����Ɩ������Ă���B���X����ʓI�ȏZ���Ƃ������Ƃ�����A�����閾�邢���r���O���[���ƍl���Ă�����Ă悢���낤�B
�掿���[�h�̐ݒ�́A��̎ʐ^�̂Ƃ���B��{�I�Ɋe�Ђ������鎩���掿�������[�h�Ƃ��Ă���B�\�j�[�uXRJ-55A95K�v�͉掿���[�h���u�X�^���_�[�h�v�Ƃ��������Łu�I�[�g�掿���[�h�v���I���BLG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�́u�W���v�Ƃ��������ŁuAI�T�[�r�X�v����uAI�f���v���v�uAI�P�x�ݒ�v�uAI�f���W�������I���v���I���B
�܂��A�����掿�������[�h�Ƃ͕ʂɉ�ʂ̖��邳�����ɍ��킹�čœK������@�\�������̂��A���ׂăI���Ƃ��Ă���B ����ł��Љ�Ă��邪�A�����Ɏg�������C���̃\�t�g�̓r�R�����甭������Ă���Ultra HD�u���[���C�u���E�� ���l�ڋ� �z�� �ЊL�܂�v�i�ȉ��u�ЊL�܂�v�j�Ɓu8K��B��i SKYWALK�`TOKYO YOKOHAMA�`�v�i�ȉ��u8K��i�v�j�B
�u�ЊL�܂�v�͉ԉΑ���4K�����8K/60p�B�e�����f���ŁA�ԉΑ��Ƃ��Ă͒��������Ԃɍs����ԉ�ЊL�܂�̗l�q�����^����Ă���B�Ȃ��A������96kHz/24bit�Ŏ��^����Ă���A���l�ڋʂ̑ł��グ�Ȃǂ͖C�e���Ɗ��Ⴂ����悤�Ȑ����������^����Ă���B
�u8K��i�v��2022�N�Ɏ��{����42V�^�L�@EL�e���r�̔�r�ł��g�p�����^�C�g���B��i�̖��邳��F�̍Č��A�[���̃O���f�[�V�����̍Č��Ȃǂ������ق��A�l�I���̖��邳�Ȃǂ̂��ߊ��S�ɍ������݂����Ă͂��Ȃ����̍Č��Ȃǂ��`�F�b�N���Ă���B
����ł���������̂́AUltra HD�u���[���C�u���E�� ���l�ڋ� �z�� �ЊL�܂�v�Ɓu8K��B��i SKYWALK�`TOKYO YOKOHAMA�`�v�B��������r�R���̍�i���B���ЁA����ł��{����Đ����Ă݂Ăق���
�u�ЊL�܂�v�̒��̉ԉ̃V�[���B���邳�┒�E�̍Č��Ȃǂɒ��ڂ�����
�u�ЊL�܂�v�̓����̂��Ղ�̗l�q�⒋�̉ԉȂǂ�����ƁA�e�e���r�̖��邳�̈Ⴂ���悭�킩��B�����邢�Ɗ������̂�LG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�ŁA���ŃV���[�v�u4T-C55FS1�v�B���҂Ƃ����Ȃ薾�邭�A�^�Ă̑��z�̃M���M���ƏƂ���銴�����悭�o�Ă���B�������邢�����łȂ��F����������Əo�Ă���̂ŕs���R�ɖ��邢�Ƃ���ʂ������ۂ��Ƃ��������͂Ȃ��B���������A�̕����͏��������Ɉ������C���ŏ������ʂ��������B
�p�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v��\�j�[�uXRJ-55A95K�v���\���ɖ��邢���ALG�G���N�g���j�N�X�A�V���[�v�ɔ�ׂ�Ƃ��T���߁B����͖����ɋP�x��~���炸�ɓ��A�̕�����������ƌ��ʂ���ȂǑS�̂̃o�����X�𐮂��Ă��邽�߂Ǝv����B�\���ɖ��邢���Õ�����������ƌ����āA���₷���f�����B�J���[�o�����X���悭�o�Ă��ċ�̐���������Əo�Ă���B
������ƌ���肵�Ă��܂����̂�TVS REGZA�u55X9900M�v�B�ق��Ɣ�ׂ�Ƃ��f�����Â��Ɗ����Ă��܂��B���ׂĂ��܂��ƁA���P�x�̉t���e���r�ƈȑO�̗L�@EL�e���r����ׂČ��Ă���悤���B
����܂łƓ���WRGB�����̃p�l���ƁA�uMLA�v���ڂ�WRGB������uQD-OLED�v�́A�p�l�����̂̋P�x���\���ڂŌ��Ă͂�����Ƃ킩��قǂɈႤ�̂��B�c�O�Ȃ��疾�邢�����ł̖��邳�����ƂȂ��TVS REGZA�͂�����ƕ��������B
���������ӂ������̂́u�p�l���ɍŐV�Z�p�����ڂ���Ă��Ȃ����獡�N��TVS REGZA�͂��߁v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����ƁB�����āATVS REGZA�ȊO�ł��]���^��WRGB�����̃p�l�����̗p�����e���r�͑�����������Ă��邱�ƁB�����ł̃e�X�g���f���ȊO�̐��i�͂قƂ�ǂ��u55X9900M�v�Ɠ����]���^��WRGB�������B���邳�ɒ��ڂ��ėL�@EL�e���r��I�ԂȂ�A����ł́u55X9900M�v�̌��������Q�l�ɂȂ邾�낤�B
�u55X9900M�v�ɂ��ĕ⑫����ƁA��ΓI�ȉ�ʂ̖��邳�ł͍������邪�F�͂�������Əo�Ă��邵�A�_�̊K������������ƕ`���Ă���B���邢��ʂł͂悳���������ɂ������A���ߍׂ����\���Ȃ�TVS REGZA�炵�����ׂ���������ƕ`���Ă����B�u55X9900M�v�͒P�ƂŌ����̐��ł����R�ȐF���Ɗ��������A�K�����Ȃǂ��܂߂Đ��n�x�͍����B�g�����ꂽ�p�l����������Ǝg�����Ȃ��Ă�����S�����������B
�܂��A��̐��͊e�Ђ̍Č��̈Ⴂ���悭�o�Ă��镔�����B�����邢LG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�͋�̐����������������₷���Ȃ邢���ۂ��A�_�̔����͗͋����B���邢�������������ꂪ���ɂ�������B
�����p�l���̃p�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v�͖��邳�������}���Ăł��_�̊K�����̐��̐[�݂܂ŕ`���Ă���B���̂�����Ō������̈Ⴂ���킩��B
���オ�Ⴄ�Ƃ͂����uQD-OLED�v�̗p�̃V���[�v�u4T-C55FS1�v�ƃ\�j�[�uXRJ-55A95K�v�́A�ǂ������̐������ԂɊ��i���F���ۂ��Ȃ�j�X��������B�����QD-OLED�p�l���̌X���ňÂ��V�[���ł����̌X�����m�F�ł����B�������A�uXRJ-55A95K�v�ł͖��邳�̃s�[�N�͂���قǗ~�����ďo�����Ƃ͂��Ă��Ȃ��B�\�j�[�掿�Ƃ��Ė��邳��F���R���g���[�����Ă���̂��낤�B
�����āu8K��i�v���Đ����Ă݂�B�[�i�̐Ԃ����܂������42V�^�L�@EL�e���r�ł��Đ������V�[�������A��͂�e�ЂňႢ���傫�������B
���邳�ł�LG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�A�V���[�v�u4T-C55FS1�v�A�p�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v����ۓI�B�X�S�̂����邭������ƁA�S�̂̌��ʂ����悢�̂��B�u�e���r��ʂ͖��邢�قǍ��掿�Ɍ�����v�Ƃ͐̂��猾���Ă������Ƃ����A����͌��݂����l���Ɗ������B
4K�Ȃ�ł͂̐��ׂ��Ƃ��f�B�e�[���܂ł悭�����āA�܂��ɑN�����Ɗ�����B��L3���f���Ō����ƁALG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v���ł����邭���ʂ����悢�B�V���[�v�u4T-C55FS1�v�͋�̐Ԃ݂�тт������Ɣ��������Ƃ̊Ԃɂ��鉩�F���L���ɏo���ہB�ԁA�A��3���F�����łȂ����ԐF���L���ɍČ����邱�Ƃɂ�������Ă���̂��킩�镔�����B�p�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v�͖��邢�����łȂ����F���F�̗[�i�̃O���f�[�V�������悭�o�Ă���B
�\�j�[�uXRJ-55A95K�v�͗[�i���炢�̖��邳�ł͉�ʑS�̖̂��邳���֒������A��̃O���f�[�V������Õ����܂߂��K����������ƕ`���Ă���B
TVS REGZA�u55X9900M�v�����l�ŁA�A�e��Z�W����������Əo�Ă���B�[�Ă��̐F�̔Z������[�݂͂�����L�������A��͂莩�R�ȕ`�ʂɂȂ��Ă���Ɗ�����B�G���̏�肳���悭�킩�镔�����B
���������ɂȂ����X�̖�i�V�[��������ƁA��ʑS�̂Ƃ��Ă͂������邭�͂Ȃ��̂�TVS REGZA�u55X9900M�v���傫������肷��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B
�����ŃR���g���X�g����V���G�b�g�ɂȂ����r���̉A�e�̍Č��Ȃǂ��Ă��˂��ɕ`���Ă���̂�TVS REGZA�u55X9900M�v�ƃp�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v�B�f��Ȃǂł����邱�Ƃ̑�����ʑS�̂��Â߂̉f�������A�����������V�[�����o�����X�悭�Č����Ă���B
�\�j�[�uXRJ-55A95K�v���R���g���X�g����o�����X�̂悳�͌����Ă���Ă����̂����A�Õ������ׂ�C���ɂȂ�X��������B�uQD-OLED�v�p�l���̑�1����͈Õ��̊K���\�����ꂵ���A�܂��m�C�Y�����ڗ����₷���X�����������̂ŁA������Ƌ�J���Ă��銴�����B
�l�I�������邭�A�X���ɏƂ炳�ꂽ���H���悭������̂�LG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�B�Õ��̕`�ʂɂ��ӗ~�������邪�A�������ׂꂪ����B�V���[�v�u4T-C55FS1�v������ɋ߂��X�����B
����������i�ł́A���Ȃ�ʓx�̍����l�I���Ȃǂ̐F���e�Ђő傫������Ă���킯�ł͂Ȃ��_�ɒ��ڂ��Ăق����B�ȑO�̔��^�e���r�ł͐F���d�������e���r�ƂȂ�ƌ��F���L�c�߂ɏo�āA�s���R�ɂȂ��Ă��܂����i���������B
���̂�����͊e�ЂƂ�������Ɛ��䂵�Ă��āA�F���h�肷����Ƃ��L�c���F�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����Ȃ��B���Ƀp�l�����̂̋P�x�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����A��萳�m�ȐF���Č����邱�Ƃ�O��ł��Ă���̂��Ǝv����B���̂��߁A��ʂ����邭�Ă��s���R�ɂȂ�Ȃ����A���邢��������Â������܂Ő������F���Č��ł��Ă���̂��B
��ʓI�ȉf���Ultra HD�u���[���C���Đ����Ă݂�
���邢���̂܂܁A�f��\�t�g�����Ă݂邱�Ƃɂ����B�M�҂̂悤�ȃ}�j�A�́A�f��͉f��ق̂悤�ɕ������Â����Č�����̂��Ǝv���Ă��邪�A�����̐l�͂����ł͂Ȃ����낤�B����z�M�����y���A���ʂɃe���r�h���}�Ȃǂ����銴�o�ʼnf����C�y�Ɍ���l�������͂����B�掿���[�h�Ȃǂ͐�قǂƓ����B
�܂��́u�~�b�V�����F�C���|�b�V�u��/�f�b�h���R�j���O PART ONE�v�BDolby Vision���^�f�B�X�N�����A5�䓯���o�͂̂���HDR10�Ńe�X�g���Ă���B���Ԃ̃��[�}�s�X�ŌJ��L����J�[�`�F�C�X�̏�ʂ��������A���Ԃ̖��邳���悭�o��̂͂�͂�LG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�ƃV���[�v�u4T-C55FS1�v�B�F���x����⍂�߂ɂȂ邱�Ƃ�����f��Ƃ͎v���ʖ��邳��������B���̂Ԃ�X�s�[�f�B�[�ȃJ�[�`�F�C�X���������悭�킩�邵�n���S�̐��H�ɓ��荞�悤�ȈÂ��V�[���ł��f���͌��₷���B
���邭�A�����Č��₷���Ȃ�LG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�����A�P�x�̃s�[�N���������f���ɔ��͂�����̂Ō��Ă��ĂȂ��Ȃ��y�����B�f��̐��E�ɓ��������o�ł͂Ȃ��A���ۂɃ��[�}�̊X�ŎB�e����Ă��錻������Ă���悤�Ȋ��o�ɂȂ�悤���B�f��炵���͌��邪���A�����͂���B
�V���[�v�u4T-C55FS1�v������ɋ߂������������A��ۓI�������̂̓t�B�A�b�g�̏��^�Ԃ̉��F���L���ɏo�邱�ƁB�L���ȉ��F�̃t�B�A�b�g500�͎��Ԃ������l�����Ȃ��Ȃ��Ǝv�����A���A���Ȏ��Ԃ̐F�Ɖ����o�Ă����B
�p�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v�����Ԃ̋�Ȃǂ͖���߂����f��炵���F���Ɩ��邳���ɋ߂Â��Ă����ۂ��B�����ꂽ�f��Ƃ��Ċ����x�̍����f��������ꂽ�̂�TVS REGZA�u55X9900M�v�ƃp�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v�B�K���\�������Ȃ̂ʼnf��炵�������┧�̊��炩���Ȃǂ��悭�o��B
�\�j�[�uXRJ-55A95K�v���悭�ł��Ă��邪�A�Õ��̊K���\���������ō����ׂ�C���Ȃ̂��c�O�B
�A�j���́u�X�p�C�_�[�}���F�A�N���X�E�U�E�X�p�C�_�[�o�[�X�v�́A�F�g������h��ʼnf���\�����a�V�Ȃ��̂��������ALG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�ƃV���[�v�u4T-C55FS1�v�͖��邭�N�₩�ȍČ��ō�i�̎��������悭�o�Ă���B����ł��h�肷����悤�Ɋ����邱�Ƃ͂Ȃ��A�F�Č����̂͐��m���B
���̂����ł̗����f���̓�����������ƁALG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�͒����x�̍����F�Č������Ɗ����邵�A�V���[�v�u4T-C55FS1�v�͒��ԐF�����L���ŔZ���ȐF�ɂȂ��Ă���Ɗ�����B�p�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v�͖���߂Ȃ�����f��炵�����G�ɋ߂Â����Č��B�K�������L���œ��ɈÐF����������ƍČ��ł��Ă���B�\�j�[�uXRJ-55A95K�v�͂��Â߂Ɋ��������A�F�͍ł��K���ʼnf��قł̈�ۂɋ߂��B�Õ��̊K�����ꂵ���̂��c�O�BTVS REGZA�u55X9900M�v���F�͐��m�Ńf�B�e�[������������Əo��̂ŁA�x�[�V�b�N�ȕ\���͂̍������悭�킩��B
�����ŁA���ꂼ��̉����ɂ��Ă��G��Ă������B����W�߂�5���f���͊e�Ђ̍ŏ�ʃ��f���̂��߉����̎��͂��Ȃ��Ȃ��̂��́B�T���E���h�����ł��L���Ȃ̂̓V���[�v�u4T-C55FS1�v�ŋ�Ԋ��܂ł悭�o��B
�p�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v�͋�Ԃ̍Č������܂����X�̉��̗͋����A�Z���t�̌��݂ȂNJ�{�I�Ȏ��͂������B
TVS REGZA�u55X9900M�v�̓T���E���h��ԂƐ��̌��݂��ʊ��̃o�����X���ǍD�B
�\�j�[�uXRJ-55A95K�v�͉�ʂ��特���o���Ɖ��̈�̊����悭�T���E���h��������Ȃ�ɂ�����邪�A��Ԋ��Ȃǂł�����ۂ������B
LG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�͔�r�I�V���v���ȍ\���̃X�s�[�J�[�V�X�e���̊��ɂ̓T���E���h�����悭�o�邪�A���А��i�Ɣ�ׂ�Ƃ�〈��肪����B�ቹ�̔��͂Ȃǂɂ��̑���Ȃ��������Ă��܂����B
���x�͕������Â��������ł̃e�X�g�B���v���߂��ĊO����������Â��Ȃ莺���Ɩ������Ƃ����B���S�ȈÎ��ł͂Ȃ����������Ƃ�̂����Â炢�Ɗ����邭�炢�A�Ǐ��͂ł��Ȃ����x���̈Â������B�掿���[�h�͏�̎ʐ^�̂Ƃ���B��������Â����ʼnf������邽�߂̉掿���[�h���B
��������f��p�̃��[�h�Ȃ̂Ő�ΓI�Ȗ��邳�͍T���߂ɂȂ�A�Â����ł�ῂ����Ɗ�����قǂł͂Ȃ��B�����āA�e�ЂƂ��ɒ����x�̍����Č��ɂȂ�B�f����Đ�����Γ��R�e�ЂƂ��ɋ߂��\���ɂȂ邪�A���ꂾ���Ɋe�Ђ̉���̈Ⴂ���悭�킩�镔���ł�����B
�f��ł͂Ȃ��u�ЊL�܂�v��u8K��i�v�̒��Ԃ̃V�[���▾�邢��ʂł́ALG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v��V���[�v�u4T-C55FS1�v�͂�����Ɩ��邭���₷���f���ɂȂ�B�f����ۂ��g�[���ɂȂ�̂��\�j�[�uXRJ-55A95K�v�A�p�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v�ATVS REGZA�u55X9900M�v�B
��܂��Ɍ����A�\�j�[�̓R���g���X�g�d���̃����n���^�A�p�i�\�j�b�N�͊K���d���ATVS REGZA�̓o�����X�^�Ƃ��ꂼ��ɈႢ�͂���B�p�i�\�j�b�N�͋Ǐ��I�ȋ���������������Əo���Ȃǃp�l���̋��݂�������Ɛ������Ă���B�\�j�[�̓p�l���̃N�Z���o�₷���Õ��ŐԂɂ��X����m�C�Y�����������邵�A�Õ����ׂ�C�����BTVS REGZA�͊K�����R���g���X�g������������Ƃ��Ă��邵�܂Ƃ܂肪�悢���A�ق��Ɣ�ׂ�Ƃ��ƂȂ�����ۂɂȂ�B
�f��n�̃��[�h�ł͍����k�܂�X���͂��邪�A�e�Ђ̉���̈Ⴂ�͊m���ɑ��݂���
��i�̃V�[���ł��ALG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v��V���[�v�u4T-C55FS1�v�͋Ǐ��I�Ȗ��邳�̍Č���������
�u�~�b�V�����F�C���|�b�V�u��/�f�b�h���R�j���O PART ONE�v�Ɓu�X�p�C�_�[�}���F�A�N���X�E�U�E�X�p�C�_�[�o�[�X�v�ł́ALG�G���N�g���j�N�X�uOLED55G3PJA�v�͖��邢�V�[���͂��Ȃ薾�邭�A�Â��V�[���͂�������Â��A�V�[���ɍ��킹�Č�������ς���B����߂���ῂ����͂Ȃ����f��炵���g�[��������B����́A���܂ł́u�f��炵���v�Ɋ��ꂽ�l�ɂ͏�����a�������邪�A�����Ĉ����Ȃ��B�V�����f��̌������Ƃ�������B
�V���[�v�u4T-C55FS1�v�����邳��N�₩������ۓI�����B�h�肳�͂�����Ɨ}���Ă��ĕs���R���͂Ȃ��B����߂̐F�̑N�₩����L�����̂悳���D�܂����B
�\�j�[�uXRJ-55A95K�v�͈Õ��Č����������Ȃ��Ƃ��C�ɂȂ���̂́A�F�̂�̂悳��R���g���X�g���͂�������Ƃ��Ă��Ă܂Ƃ܂�͂悢�B
�p�i�\�j�b�N�uTH-55MZ2500�v��TVS REGZA�u55X9900M�v�͉f��I�Ȋ��G����������Əo���������B�p�i�\�j�b�N���Õ����������K������L���ɕ`���ĉf��炵���g�[���Ə��ʂ���������Ɠ`����̂ɑ��āATVS REGZA�̓f�B�e�[�����k������p�m���}�I�Ȍi�F�̗��̊����������B
�������͊e�Ђ̍ŏ�ʃN���X�̗L�@EL�e���r�ƌ����ׂ����A��������g�[�^���ł̎��͂͂��Ȃ荂���B�ŐV�L�@EL�e���r�ł́A�p�l���̈Ⴂ�Ŋe�Ђ̌�������ɋ��܂����Ɗ������B
�p�i�\�j�b�N�́uTH-55MZ2500�v�͈Â������ʼnf����ӏ܂���Ƃ����ϓ_�Ō����A�����_�ł͍ł��D�G�ȃe���r�ƌ����Ă悢�B���P�x�����ʂ������p�l���̎��͂���������ƈ����o���A�p�i�\�j�b�N�̎������ł���K�����Ȃǂ�����ɂ����ꂽ���̂ɂ��Ă���B�����X�s�[�J�[�ɂ��Ă�����ȃT�E���h�o�[���D�G�Ȃ��炢�ŁA���������ɃA�b�v�O���[�h����Ȃ�AV�A���v�ƃX�s�[�J�[�ɂ��T���E���h����������ׂ����x���B
LG�G���N�g���j�N�X�́uOLED55G3PJA�v�̓����́A�Ȃ�ƌ����Ă���ʂ̖��邳���B�����ɖ��邭���ĉ�ʂ������ۂ��Ƃ������Ƃ��Ȃ��A�F�͐��m�œ��ᎋ�ɋ߂�������������B���̓_�ł̓h�L�������^���[��i��e���r�������������Ƃ����l�ɍ����B�f���������Ɗy���߂���͂͂���̂ŁA���i���疾�邢�����ʼnf�������Ƃ����l�ɓK���Ă��邾�낤�B�����Ɋւ��Ă͑��ЂƔ�ׂĂ��n��Ȃ̂ŁA�T�E���h�o�[�Ȃǂ̒lj����l�������Ƃ���B
�V���[�v�́u4T-C55FS1�v�����邢�����ł��܂��܂ȉf���𑶕��Ɋy���߂����B�p�l���̍��P�x�ƖL���ȐF����������ƈ����o���āA����܂ł̃V���[�v�掿�����������N���߂��\�����ł��Ă���B�p�l���̓����������ď����Ԋ��ɂȂ�X���͂��邪�s���R�Ɋ�����قǂł͂Ȃ��B���Ɋւ��Ă��T���E���h�̍L���芴���L�������A���͂̍����X�s�[�J�[�����������Ɏg�p���Ă����{�I�Ȏ��͂������B
�\�j�[�́uXRJ-55A95K�v��1�N�O�̃��f���Ƃ����n���f�������ĈÕ��K���Ȃǂŏ������������镔�������������̂��c�O�B��������{�I�Ȏ��͂͏\���ɗD�G�����A���i�����Ȃ�Ă���̂ł���������������B�����ۂ��ł��낻��2024�N�̐V���f�������o�n�߂�^�C�~���O�Ȃ̂ŁA����Ȃ�i�����ʂ������ŐV���f���ɒ��ڂ���̂��肾�B�����̎��͓I�ɑ傫�ȕs���͂Ȃ����A�T���E���h�𑶕��Ɋy���ނȂ�T�E���h�o�[�Ȃǂ������������Ƃ���B
TVS REGZA�́u55X9900M�v�̓p�l���̈Ⴂ�ŁA���ЂƂ悳���A�s�[���ł��Ă��Ȃ������͂���B���P�x�p�l�����̗p������p�@�ɂ����҂������Ƃ���B�������A�f��掿�̊����x�̍����A����̓e�X�g���Ă��Ȃ����e���r�����Ȃǂł̎����Č���f�B�e�[�������̎��͂̍����ȂǁA���܂��܂ȉf���Ŕ������f�����y���߂鑍���͂̍����͂���B���������Ȃ�̂��̂ŏd�ቹ�Đ����\�������A6�`�����l���S�^�Ƃ����ق��ɂ͂Ȃ����������B�������Â����ĉf�������l�ȂǁA��ʂ̖��邳�ɂ����܂ł������Ȃ��l�Ȃ�f�����b�g�͂قƂ�ǂȂ��B
������̋L���ɍ��킹�āA�e�Ђ̉f�����r�ł��铮��R���e���c�����ЎQ�l�ɂ��Ăق����B�p�l���̖��邳�̈Ⴂ���v���������傫�����Ƃ��悭�킩���Ă��炦��Ǝv���B���ł�2024�N���f���̏�o�n�߂�^�C�~���O�ł͂��邪�A�e�Ђ��̗p�����p�l���̓�����X���Ȃǂ͗��N���f���ł������p�����Ǝv���̂ł����������̎Q�l�ɂ��Ȃ�Ǝv���B


















![LAVIE Tab EX TX117/LAS PC-TX117LAS [�V�[�V�F��]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001767443.jpg)

![TW-DV7A [�z���C�g]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001764902.jpg)
![SOLOTA NP-TMLK1-K [�u���b�N]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001764447.jpg)