クレジットカードの「2枚持ち」は、
・おトクに買い物できる店舗・サービスが増え、より多くのポイント獲得が期待できる
・カードを盗難、紛失などしてしまったときの備えになる
・異なる国際ブランドのカードを持つことで、利用店舗が広がる
などのメリットがあります。
では、具体的にどういった組み合わせがポイント獲得などの面で有利なのか。100枚以上のクレジットカードを保有し、ポイント、カードのポータルサイト「ポイ探」を運営する菊地崇仁さんに、おすすめの5つのパターンと使い方を解説してもらいました。
〈1〉スタンダードな組み合わせの2枚持ち
| カード | 画像 | 入会特典 | 詳細を見る | 年会費 | ポイント還元率 | 貯まるポイント | ポイントの主な使い道 | カードの特徴 | 国際ブランド | 付帯保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天カード | 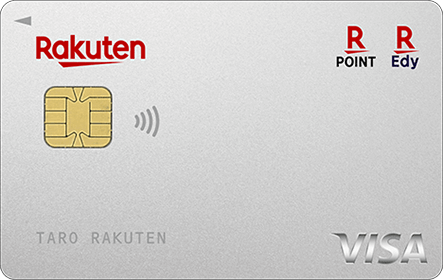 |
最大5,000円相当 プレゼント |
詳細を見る公式サイトへ | 無料 | 1.0%〜3.0% | 楽天ポイント | カード代金に充当 楽天ペイでの買い物で利用 |
楽天市場で3%還元 基本還元率が高水準 |
Visa、Mastercard、JCB、AMEX | 海外旅行/最高2,000万円 |
| 三井住友カード(NL) |  |
最大5,500円相当 プレゼント |
詳細を見る価格.comへ | 無料 | 0.5%〜7.0% | Vポイント | カード代金に充当 Visaタッチ決済で利用 |
対象のコンビニ、飲食店で タッチ決済(スマホ)をすると7%還元 |
Visa、Mastercard | 海外旅行/最高2,000万円 (旅行以外の補償を選択可能) |
〈2〉Amazonユーザー向けの2枚持ち
| カード | 画像 | 入会特典 | 詳細を見る | 年会費 | ポイント還元率 | 貯まるポイント | ポイントの主な使い道 | カードの特徴 | 国際ブランド | 付帯保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB CARD W |  |
最大45,500円相当 プレゼント |
詳細を見る公式サイトへ | 無料 | 1.0%〜10.5% | Oki Dokiポイント | nanacoポイントに交換(1P=4.5P) Amazonでの買い物に利用(1P=3.5円) |
Amazonで2%還元 基本還元率が1%と高水準 |
JCB | 海外旅行/最高2,000万円 ショッピング(海外)/最高100万円 |
| 三菱UFJカード |  |
― | 詳細を見る価格.comへ | 無料 | 0.5%〜7.0% | グローバルポイント | Amazonギフト券に交換 Visaタッチ決済で利用 |
対象のコンビニ、飲食店で7%還元 | Visa、Mastercard、JCB、AMEX | 海外旅行/最高2,000万円 ショッピング(海外・国内)最高100万円 ※国内はリボ・分割の場合のみ |
〈3〉PayPayユーザー向けの2枚持ち
| カード | 画像 | 入会特典 | 詳細を見る | 年会費 | ポイント還元率 | 貯まるポイント | ポイントの主な使い道 | カードの特徴 | 国際ブランド | 付帯保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPayカード |  |
― | 詳細を見る公式サイトへ | 無料 | 1.0%〜5.0% | PayPayポイント | PayPayでの買い物に利用 | PayPay利用時に最大1.5%還元に Yahoo!ショッピングで最大5%還元 |
Visa、Mastercard、JCB | |
| ビューカード スタンダード |  |
最大10,000円相当 プレゼント |
詳細を見る公式サイトへ | 524円 | 0.5%〜5.0% | JRE POINT | Suicaにチャージ JR東日本の駅ビルで利用 |
モバイルSuicaへのチャージで1.5%還元 モバイルSuica定期券で5%還元 |
Visa、Mastercard、JCB | 海外旅行/最高500万円 国内旅行/最高1,000万円ショッピング |
〈4〉高コスパなゴールドカードを軸にした2枚持ち
| カード | 画像 | 入会特典 | 詳細を見る | 年会費 | ポイント還元率 | 貯まるポイント | ポイントの主な使い道 | カードの特徴 | 国際ブランド | 付帯保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友カード ゴールド(NL) |  |
最大7,500円相当 プレゼント |
詳細を見る価格.comへ | 5,500円(条件付き無料) | 0.5%〜7.0% | Vポイント | カード代金に充当 Visaタッチ決済で利用 |
対象店でのタッチ決済(スマホ)で7%還元 年100万円利用で翌年以降の年会費が無料 |
Visa、Mastercard | 海外・国内旅行/最高2,000万円 (旅行以外の補償を選択可能) |
| P-one カード<Standard> |  |
― | 詳細を見る価格.comへ | 無料 | 1.0% | ― | ― | カード利用金額の1%が 請求時に自動で1%オフ |
Visa、Mastercard、JCB |
〈5〉新幹線の利用が多い方向けの2枚持ち
| カード | 画像 | 入会特典 | 詳細を見る | 年会費 | ポイント還元率 | 貯まるポイント | ポイントの主な使い道 | カードの特徴 | 国際ブランド | 付帯保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビューカード ゴールド |  |
最大30,000円相当 プレゼント |
詳細を見る公式サイトへ | 11,000円 | 0.5%〜10.0% | JRE POINT | Suicaにチャージ JRの駅ビルで利用 |
Suicaへのオートチャージで1.5%還元 新幹線eチケット購入で10%還元 |
Visa、JCB | 海外・国内旅行/最高5,000万円 ショッピング(海外・国内)最高300万円 |
| JCBカード S | 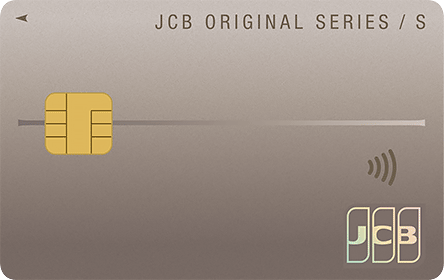 |
最大45,500円相当 プレゼント |
詳細を見る公式サイトへ | 無料 | 0.5%〜10.0% | Oki Dokiポイント | nanacoポイントに交換(1P=4.5P) Amazonでの買い物に利用(1P=3.5円) |
対象のレジャー施設、飲食店で最大80%オフ スマホ保険が付帯 |
JCB | 海外旅行/最高2,000万円 ショッピング(海外)/最高100万円 |
入会特典の内容は2025年12月1日時点の情報を掲載しています。カード入会の際は、必ず公式HPで特典内容をご確認ください。
〈菊地崇仁さん〉北海道札幌市出身。日本電信電話株式会社(現NTT東日本)を退社後、友人と起業したシステム設計・開発・運用会社を経て、2006年にポイント交換案内サービス「ポイ探」の開発に携わり、2011年3月代表取締役に就任。以後、ポイント、クレジットカード、マイレージに関する豊富な知識を生かし、テレビや雑誌などでも活躍中
(以下、菊地崇仁さん語り)
本来、管理の面から考えると、カードの保有は「1枚だけ」とするのが理想的なのかもしれません。ただし1枚だけだと、どうしてもポイント獲得の面では“取りこぼし”が出てきます。
あらゆるシーンでいつもおトクになるカードは存在せず、各カードには強みと弱みがあるからです。
たとえば、「基本のポイント還元率は1%と高水準、でもそのほかに目立った特徴はない」カードだけだと、得られるポイント数は利用額の1%にとどまります。これに、「基本の還元率は0.5%と並みの水準、しかし、特定の大手チェーン店では5%還元」のカードを保有し、この2枚を使い分けていけば、1枚持ちのときより多くのポイント獲得が期待できます。
2枚持ちは“もしも”の場合への備えにもなります。
クレジットカードのICチップに不具合が生じたり、紛失や不正利用の被害にあったりしたときには、カード会社に再発行を依頼することになります。このとき、1枚しか保有していないと、新しいカードが手元に届くまでの1、2週間の間、クレジットカードの使用ができなくなります。
さらに、利用先を広げる意味でも、2枚持ちは有効策になります。クレジットカードの券面には「Visa」「Mastercard」「JCB」「Amex」「ダイナース」などのロゴが入っており、これらは国際ブランドを示しています(この5つは5大ブランドと呼ばれています)。
たとえばVisaブランドのカードであれば世界中のVisa加盟店で利用可能です。1枚のカードに付いている国際ブランドはひとつのみなので、異なる国際ブランドのカードを持っておくことで、利用できるお店の選択肢が広がります。
特に海外では「Visa」と「Mastercard」の二大ブランドしか使えない店も少なくないため、海外利用を考えている場合、2枚のうち1枚はこの2つのブランドから選んでおくのが無難でしょう。
クレジットカードには、「Visa」「Mastercard」「JCB」などの国際ブランドのロゴが入っています
では、2枚持ちする場合、どのような組み合わせでカードを選べばよいのでしょうか。
まずは自身がよく利用する店舗・サービスを加味して、最もメリットが大きくなるメインカードを決定。次にメインカードにはない特典が付帯、あるいはメインの弱点を補う特徴を持つサブカードを探す、という流れが基本的な考え方になります。
もちろん、最適な組み合わせはライフスタイルによって千差万別。万人に共通する2枚持ちの最適な組み合わせは提示できませんが、該当者も多いと予想され、利用シーン別に私がメリットが大きいと考える具体的な2枚持ちの組み合わせを紹介していきます。
| カード | 画像 | 入会特典 | 詳細を見る | 年会費 | ポイント還元率 | 貯まるポイント | ポイントの主な使い道 | カードの特徴 | 国際ブランド | 付帯保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天カード | 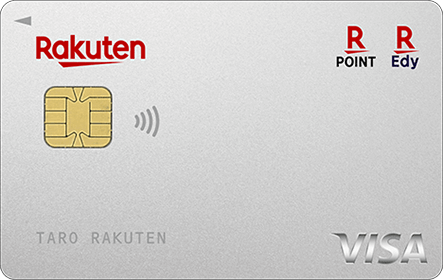 |
最大5,000円相当 プレゼント |
詳細を見る公式サイトへ | 無料 | 1.0%〜3.0% | 楽天ポイント | カード代金に充当 楽天ペイでの買い物で利用 |
楽天市場で3%還元 基本還元率が高水準 |
Visa、Mastercard、JCB、AMEX | 海外旅行/最高2,000万円 |
| 三井住友カード(NL) |  |
最大5,500円相当 プレゼント |
詳細を見る価格.comへ | 無料 | 0.5%〜7.0% | Vポイント | カード代金に充当 Visaタッチ決済で利用 |
対象のコンビニ、飲食店で タッチ決済(スマホ)をすると7%還元 |
Visa、Mastercard | 海外旅行/最高2,000万円 (旅行以外の補償を選択可能) |
「楽天カード」と「三井住友カード(NL)」の組み合わせは、幅広いユーザーにメリットがありそうです
最初に紹介するのが、最もオーソドックスな2枚持ちの組み合わせです。
「楽天カード」は年会費無料。基本のポイント還元率は1%で、100円ごとに「楽天ポイント」が1P貯まります。さらに、楽天市場の買い物では3%還元にアップするなど、楽天ユーザーにはメリットの大きいカードです。
いっぽうの「三井住友カード(NL)」も年会費無料。200円ごとに「Vポイント」が1P貯まり、基本のポイント還元率は0.5%。この数字は平均的ですが、セブン‐イレブンやローソン、マクドナルドなどでスマホのタッチ決済をすると7%還元にアップ(セブン-イレブンは最大10%)する特典が魅力的です。
※スマホのタッチ決済による、飲食チェーンなどでの7%還元やセブン‐イレブンでの10%還元は、各種条件が設定されています。詳細は下記の公式HPをご確認ください
三井住友カード公式HP
この組み合わせの場合、買い物などの普段使い、および楽天市場を使うときは「楽天カード」を利用、7%還元となるコンビニやマクドナルド、ファミレスチェーンでは「三井住友カード(NL)」でタッチ決済(スマホ)、という使い分けがおすすめ。
「楽天カード」はポイ活をする際の定番アイテムで、貯まる「楽天ポイント」も楽天ペイでの決済やカード代金に充当でき、使い勝手は抜群。また、三井住友カード(NL)」で7%還元になるお店はコンビニ、外食チェーンを中心に身近な店舗が多く対象となっています。
そのためこの2枚は、若年層からファミリー層まで幅広いユーザーにメリットのある組み合わせと言えそうです。また、楽天カードの場合、AMEXを含む4つの国際ブランドから選べるのも利点になるでしょう。
●楽天カード
年会費:無料
国際ブランド:Visa、Mastercard、JCB、AMEX
貯まるポイント:楽天ポイント(1P=1円相当)
基本ポイント還元率:1%(100円で1P)
主要な特典:楽天市場で3%還元
●三井住友カード(NL)
年会費:無料
国際ブランド:Visa、Mastercard
貯まるポイント:Vポイント(1P=1円相当)
基本ポイント還元率:0.5%(200円で1P)
主要な特典:セブン‐イレブンやローソン、マクドナルドなどの対象店でのタッチ決済(スマホによる)でポイント最大7%還元(セブン-イレブンは最大10%)
| カード | 画像 | 入会特典 | 詳細を見る | 年会費 | ポイント還元率 | 貯まるポイント | ポイントの主な使い道 | カードの特徴 | 国際ブランド | 付帯保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB CARD W |  |
最大45,500円相当 プレゼント |
詳細を見る公式サイトへ | 無料 | 1.0%〜10.5% | Oki Dokiポイント | nanacoポイントに交換(1P=4.5P) Amazonでの買い物に利用(1P=3.5円) |
Amazonで2%還元 基本還元率が1%と高水準 |
JCB | 海外旅行/最高2,000万円 ショッピング(海外)/最高100万円 |
| 三菱UFJカード |  |
― | 詳細を見る価格.comへ | 無料 | 0.5%〜7.0% | グローバルポイント | Amazonギフト券に交換 Visaタッチ決済で利用 |
対象のコンビニ、飲食店で7%還元 | Visa、Mastercard、JCB、AMEX | 海外旅行/最高2,000万円 ショッピング(海外・国内)最高100万円 ※国内はリボ・分割の場合のみ |
「JCB CARD W」と「三菱UFJカード」はAmazonユーザー、かつオーケーなどのスーパーで買い物をする機会が多い方にはメリット
続いては、Amazonをよく使う人にメリットのある2枚持ちのパターンです。
「JCB CARD W」は年会費無料。通常では1,000円ごとに「Oki Dokiポイント」が2P(1P=最大5円相当)貯まるため、基本のポイント還元率は1%相当。ほかのJCBプロパーカードより2倍の還元率になります。
また、Amazonやセブン‐イレブンでは最大2%還元相当、スターバックスへのオンライン入金では5.5%還元相当にアップするのが魅力です(登録作業が必要)。ただし、このカードは39歳以下限定での申し込みとなります(1度入会すれば、40歳以降でも利用可能です)。
いっぽうの「三菱UFJカード」は1,000円ごとに「グルーバルポイント」が1P(1P=最大5円相当)貯まり、基本のポイント還元率は0.5%相当。セブン‐イレブンやスーパーのオーケー、くら寿司やスシロー、松屋では7%還元相当(1,000円で14P)にアップします(ただし、7%還元は対象店での利用が月間5万円まで、それを超えると0.5%還元にダウン)。
さらに、三菱UFJ銀行の口座を引き落とし口座に設定するなど、三菱UFJグループの金融サービスの利用状況に応じて、対象店での還元率を最大20%にまで上げることが可能です。
〈「三菱UFJカード」のポイントアップの対象店〉
〈コンビニ〉
セブン‐イレブン、ローソン(ナチュラルローソン、ローソンストア100を含む)
〈飲食店〉
くら寿司、スシロー、ピザハットオンライン、松屋、松のや、マイカリー食堂、ロッテリア、ゼッテリア
〈スーパー〉
オーケー、オオゼキ、三和、フードワン、スーパー魚長、生鮮げんき市場、生鮮乃木市場、東武ストア、ドミー、肉のハナマサ、ジャパンミート、ヤマナカ、フランテ、フランテロゼ、アオキスーパー、サンリブ、キンショー、ハーベス、東急ストア
〈自販機〉
コカ・コーラ自販機
※アメックスブランドの場合、くら寿司、オーケー、オオゼキ、三和、フードワン、スーパー魚長、生鮮げんき市場、生鮮乃木市場、ドミー、肉のハナマサ、ジャパンミート、ロッテリア、アオキスーパー、東急ストアは対象外
この組み合わせの場合、普段使いとAmazonでは「JCB CARD W」を使い、オーケーや松屋、くら寿司などの7%還元対象店では「三菱UFJカード」を使っていくのが効果的と言えそうです。
なお今回は、
・「楽天カード」×「三井住友カード(NL)」
・「JCB CARD W」×「三菱UFJカード」
という組み合わせを紹介しましたが、サブカードをそれぞれ入れ替えて、
・「楽天カード」×「三菱UFJカード」
・「JCB CARD W」×「三井住友カード(NL)」
という組み合わせも十分に検討に値します。
「三井住友カード(NL)」と「三菱UFJカード」のスペックは似ていますが、ポイント優遇店が前者は飲食チェーンやコンビニが中心なのに対し、後者は食品スーパーが多く対象になっている点に違いがあります。
ライフスタイルにあわせて、メインカードのスペックを備えた「楽天カード」と「JCB CARD W」、サブカードにピッタリな「三井住友カード(NL)」と「三菱UFJカード」を上手に組み合わせるとよいでしょう。
●JCB CARD W
年会費:無料
国際ブランド:JCB
貯まるポイントOki Dokiポイント(1P=3〜5円相当)
基本ポイント還元率:0.6〜1%(1,000円で2P)
主要な特典:セブン‐イレブンとAmazonで2%還元
●三菱UFJカード
年会費:無料
国際ブランド:Visa、Mastercard、JCB、AMEX
貯まるポイント:グローバルポイント(1P=5円相当)
基本ポイント還元率:0.5%(1,000円で1P)
主要な特典:セブン‐イレブンやローソン、スーパーのオーケーなどで7%還元
| カード | 画像 | 入会特典 | 詳細を見る | 年会費 | ポイント還元率 | 貯まるポイント | ポイントの主な使い道 | カードの特徴 | 国際ブランド | 付帯保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPayカード |  |
― | 詳細を見る公式サイトへ | 無料 | 1.0%〜5.0% | PayPayポイント | PayPayでの買い物に利用 | PayPay利用時に最大1.5%還元に Yahoo!ショッピングで最大5%還元 |
Visa、Mastercard、JCB | |
| ビューカード スタンダード |  |
最大10,000円相当 プレゼント |
詳細を見る公式サイトへ | 524円 | 0.5%〜5.0% | JRE POINT | Suicaにチャージ JRの駅ビルで利用 |
モバイルSuicaへのチャージで1.5%還元 モバイルSuica定期券で5%還元 |
Visa、Mastercard、JCB | 海外旅行/最高500万円 国内旅行/最高1,000万円ショッピング |
「PayPay」と相性抜群の「PayPayカード」
続いては、ユーザー数7,000万人超、コード決済で断トツのシェアを誇る「PayPay」ユーザーにおすすめの組み合わせです。
「PayPayカード」は年会費無料。通常時には、200円で「PayPayポイント」が2P貯まり、基本のポイント還元率は1%。
「PayPay」との相性のよさがこのカードの特徴で、事前に「PayPayカード」をひもづけておけば、口座などからのチャージ不要で「PayPay」で決済ができます(この決済方法は「PayPayクレジット払い」と呼ばれています)。
また、「PayPay」や「PayPayカード(クレジット利用設定済みの場合)」の利用が「30回以上&月間10万円以上」という条件を達成した翌月は、「PayPayクレジット払い」の還元率が1.5%にまでアップするのも利点です(通常の「PayPay残高払い」の還元率は最大1.0%)。
いっぽうの「ビューカード スタンダード」は年会費524円。通常利用時には1,000円で「JRE POINT」が5P貯まり、基本のポイント還元率は0.5%。
このカードの大きな魅力は、JR東日本のサービス利用時には還元率がアップする点にあり、モバイルSuicaへチャージ(オートチャージ含む)すると1.5%還元(1,000円で15P)、モバイルSuica定期券の購入では5%還元になります。
この組み合わせの場合、主に使うのは「PayPayクレジット払い」。「PayPay」は中小店舗から大手チェーンまで利用可能な店舗は豊富にあり、「買い物」の多くの部分をカバーできるでしょう。
そして、「PayPayカード」でモバイルSuicaやApple PayのSuicaにチャージしても1%分貯めることができますが、スマホにモバイルSuicaのアプリを入れておき、「ビューカード スタンダード」からオートチャージの設定をしておけば、「移動」もよりスムーズに、よりオトクにできそうです。
●PayPayカード
年会費:無料
国際ブランド:Visa、Mastercard、JCB
貯まるポイント:PayPayポイント(1P=1円相当)
基本ポイント還元率:1%(100円で1P)
主要な特典:PayPayをチャージ不要で使えて、還元率を最大1.5%にできるカード
●ビューカード スタンダード
年会費:524円
国際ブランド:Visa、Mastercard、JCB
貯まるポイント:JRE POINT(1P=1円相当)
基本ポイント還元率:0.5%(1,000円で5P)
主要な特典:モバイルSuicaへのオートチャージ・チャージで1.5%還元
| カード | 画像 | 入会特典 | 詳細を見る | 年会費 | ポイント還元率 | 貯まるポイント | ポイントの主な使い道 | カードの特徴 | 国際ブランド | 付帯保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友カード ゴールド(NL) |  |
最大7,500円相当 プレゼント |
詳細を見る価格.comへ | 5,500円(条件付き無料) | 0.5%〜7.0% | Vポイント | カード代金に充当 Visaタッチ決済で利用 |
対象店でのタッチ決済(スマホ)で7%還元 年100万円利用で翌年以降の年会費が無料 |
Visa、Mastercard | 海外・国内旅行/最高2,000万円 (旅行以外の補償を選択可能) |
| P-one カード<Standard> |  |
― | 詳細を見る価格.comへ | 無料 | 1.0% | ― | ― | カード利用金額の1%が 請求時に自動で1%オフ |
Visa、Mastercard、JCB |
「三井住友カード ゴールド(NL)」と「P-one カード<Standard>」の組み合わせ。こちらはゴールド特典を利用しながら、高い還元を受けられるのが魅力
続いては、高コスパなゴールドカードを軸にした2枚持ちの組み合わせです。
「三井住友カード ゴールド(NL)」は年会費5,500円。通常時は200円利用で「Vポイント」が1P貯まり、基本のポイント還元率は0.5%になります。
前述の「三井住友カード(NL)」からランクアップしたカードで、国内およびハワイの空港ラウンジが利用できるほか、最高300万円のショッピング保険が付帯しています。
このカードのメリットが大きくなるのは100万円利用したとき。年間100万円利用すると、継続特典として10,000Pがプレゼントされるため、100万円利用時には15,000Pが付与され、還元率は1.5%にまでアップします。
さらに、100万円利用した翌年以降は年会費が継続して無料になり、コストを負担することなく、空港ラウンジなどのゴールド特典を利用できるのも魅力になっています。
※年間100万円利用の対象取引や算定期間などの詳細については、下記の公式HPをご確認ください
三井住友カード公式HP
いっぽう、伊藤忠商事などが出資するポケットカードが発行する「P-one カード<Standard>」は年会費無料。このカードは、利用金額に対して「ポイント還元」されるのではなく、1%分が自動で請求額から割り引かれるのが特徴的です。
たとえば、50,000円利用した月の請求額は49,500円(50,000円−500円)に。ショッピングはもちろん、公共料金や税金などの支払いも対象で、もらったポイントの使い道を考える必要がなく、シンプルに使えるのがこのカードの大きな利点になります。
前述のとおり、「三井住友カード ゴールド(NL)」は、継続特典の10,000Pがプレゼントされる年間100万円ちょうど利用したときに、実質の還元率が最も高い1.5%になります。いっぽうで、年間100万円を超えて利用していくと、基本のポイント還元率が「0.5%」であるために、実質的な還元率はだんだん下がっていきます。
「三井住友カード ゴールド(NL)」の還元率
年間100万円未満の利用:0.5%還元
年間100万円の利用:1.5%還元(15,000ポイント付与)
年間200万円の利用:1%還元(20,000ポイント付与)
年間300万円の利用:0.83%還元(25,000ポイント付与)
年間400万円の利用:0.75%還元(30,000ポイント付与)
つまり、年間100万円までは「三井住友カード ゴールド(NL)」を使って、10,000Pの継続特典を受け取る。そして、100万円以降は自動で1%オフとなる「P-one カード<Standard>」を利用していく。こうすることで、空港ラウンジなどのゴールド特典を利用しつつ、常に1%を超えるポイント還元や割引きを受けることができそうです。
●三井住友カード ゴールド(NL)
年会費:5,500円
国際ブランド:Visa、Mastercard
貯まるポイント:Vポイント(1P=1円相当)
基本ポイント還元率:0.5%(200円で1P)
主要な特典:年間100万円の利用で10,000Pがプレゼントされ、翌年以降の年会費が無料に
●P-one カード<Standard>
年会費:無料
国際ブランド:Visa、Mastercard、JCB
基本還元率:1%(100円で1円)
主要な特典:カードを使うと自動で、自動的に請求時に100円ごとに1円がオフに
| カード | 画像 | 入会特典 | 詳細を見る | 年会費 | ポイント還元率 | 貯まるポイント | ポイントの主な使い道 | カードの特徴 | 国際ブランド | 付帯保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビューカード ゴールド |  |
最大30,000円相当 プレゼント |
詳細を見る公式サイトへ | 11,000円 | 0.5%〜10.0% | JRE POINT | Suicaにチャージ JRの駅ビルで利用 |
Suicaへのオートチャージで1.5%還元 新幹線eチケット購入で10%還元 |
Visa、JCB | 海外・国内旅行/最高5,000万円 ショッピング(海外・国内)最高300万円 |
| JCBカード S | 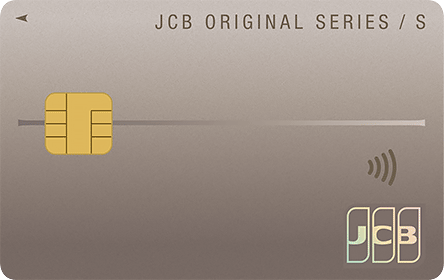 |
最大45,500円相当 プレゼント |
詳細を見る公式サイトへ | 無料 | 0.5%〜10.0% | Oki Dokiポイント | nanacoポイントに交換(1P=4.5P) Amazonでの買い物に利用(1P=3.5円) |
対象のレジャー施設、飲食店で最大80%オフ スマホ保険が付帯 |
JCB | 海外旅行/最高2,000万円 ショッピング(海外)/最高100万円 |
最後に紹介するのが、新幹線を使っての旅行や出張が多い方向けの組み合わせです。
「ビューカード ゴールド」は年会費11,000円。通常時は1,000円利用で「JRE POINT」が5P貯まり、基本のポイント還元率は0.5%です。
この部分は「ビューカード スタンダード」と同様ですが、JR東日本のサービス利用時の還元率は大幅にアップし、新幹線eチケットでチケットレス乗車をすると10%還元となります(通常のビューカードは5%還元)。たとえば、「東京―金沢」を1往復すると2,806Pが還元され、年間4回程度の新幹線利用があれば、年会費分のポイントは獲得可能です。
また、えきねっとではJR東海の新幹線やJR北海道の特急列車などのチケットも購入できます。eチケットサービスの利用はできず10%にはなりませんが、8%分のポイントを獲得できます。
このほか、モバイルSuicaのグリーン券購入では10%還元、定期券購入では6%還元となるなど、JR東日本のサービスを定期的に利用するなら持っておいて損のないゴールドカードと言えそうです。
「ビューカード ゴールド」の利用機会が多い方にピッタリなサブカードが「JCBカード S」です。
このカードは年会費無料。基本のポイント還元率は0.5%と平均的な水準ですが、「クラブオフ」という割引き特典が付帯しているのが大きな魅力。「クラブオフ」を使うと、各地のレストランやホテル、遊園地など、国内外20万か所以上の施設やサービスで最大8割引きとなります。
新幹線移動の際は「ビューカード ゴールド」を使って10%分の「JRE POINT」を獲得。旅先のレジャー施設やホテル、レンタカー利用時には「JCBカード S」を使って割引きを受けることができれば、おトクな旅を経験できそうです。
●ビューカード ゴールド
年会費:11,000円
国際ブランド:Visa、JCB
貯まるポイント:JRE POINT(1P=1円相当)
基本ポイント還元率:0.5%(1,000円で5P)
主要な特典:新幹線のeチケット予約で最大10%還元
●JCBカード S
年会費:無料
国際ブランド:JCB
貯まるポイント:Oki Dokiポイント(1P=3〜5円相当)
基本ポイント還元率:0.3〜0.5%(1,000円で1P)
主要な特典:各地のレジャー施設やホテル、飲食店で割引きが受けられる「クラブオフ」の特典が利用可能
ここまでは「2枚持ち」のメリットと、おすすめの5パターンを紹介してきましたが、気をつけておきたい点もあります。
ひとつは申し込みのタイミング。複数のカード会社に同じ時期に入会を申し込む「多重申し込み」は不正な目的や、支払い能力があるのか疑問視されるため、避けたほうがよいとされています。
私自身過去に2枚同時に申し込みを行い、どちらも無事に審査に通ったので、2枚程度なら問題ないこともあるようです。ただ、カードの申込履歴は信用情報機関に過去6か月間分が記録されるため、審査が心配な場合は6か月は間を開けて申し込むのがよさそうです。
2つ目はカードの不正利用対策です。クレジットカードの2023年の不正利用被害額は540億円で過去最悪となり、ここ10年で5倍の規模に被害が拡大しています。
フィッシングやスキミングなど、不正利用の手口は巧妙化しており、被害を完全に防ぐのは難しいのが実情です。事前に100%防げない以上、利用明細をチェックして身に覚えのない請求の有無をチェックする作業は不可欠です(基本的にどのカード会社でも、申告からさかのぼって60日前までの不正利用は補償されます)。
1枚持ちのときより2倍の手間がかかりますが、アプリなどで明細を定期的に確認するようにしましょう。
3つ目は、サブカードのポイントの有効期限です。サブカードではメインカードと比べて利用額が低くなり、貯まるポイントも少なくなるでしょう。
ポイントサービスによっては、利用・交換にあたって最低限の数量を定めているケースも少なくありません(「利用・交換は最低200ポイントから」など)。そのため、有効期限内にサブカードのポイントを一定数貯められ、なおかつ消化できるのか、ある程度シミュレーションしておくとよいでしょう。
カード会社ごとに異なる、利用金額の締め日と引き落とし日も見ておく必要があります。下記に今回紹介したカード会社のスケジュールを記載しておきましたが、口座の残高が不足しないよう事前に確認しておきましょう。
〈主要カード会社の締め日と引き落とし日〉
楽天カード:毎月末日締め翌月27日払い
三井住友カード:毎月15日締め翌月10日払いor毎月末日締め翌月26日払い(選択制)
JCB:毎月15日締め翌月10日払い
三菱UFJニコス:毎月15日締め翌月10日払い
PayPayカード:毎月末日締め翌月27日払い
ビューカード:毎月5日締め翌月4日払い
ポケットカード:毎月1日締め翌月1日払い
以上、クレジットカードの「2枚持ち」のメリットと、その具体例を紹介してきました。
2枚持ちを検討する際は、
メインカード
→基本の還元率が高い、あるいは自身がよく使うサービスで高還元を得られるものを選択
サブカード
→メインカードでは足りない要素を補完できるカード
を選ぶのが基本的な考え方になります。
また、利用機会の少ないサブカードについては年会費が無料、あるいは手ごろな年会費のものを選ぶのが無難でしょう。
今回は、多くの人がメリットを感じやすいと考える5つの組み合わせを紹介してきましたが、ライフスタイルによって「正解」は異なってきます。紹介した組み合わせも参考に、自身によってメリットの大きい“最強の2枚”を検討してみてください。
下記記事では、年会費が無料で高還元であったり、特定サービスで10%ものポイント還元を受けられたりする価格.comで人気の10枚のカードを紹介してます。気になる方はチェックしてみてください。


















![Galaxy Tab A11+ 5G SIMフリー [グレー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001721970.jpg)
![フォクトレンダー APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical [ソニーE用]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001719908.jpg)
![Modern-13-F1MOG-5589JP [プラチナグレイ]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001722838.jpg)
![TRINITY AZL-TRINITY-ST-MNT [Frozen Mint]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001722383.jpg)