みんなで大画面を囲むなら、プロジェクターの大画面がいちばんです。プロジェクターの再人気でまずは壁投写で楽しむ人が増えていますが、スクリーンに映すと見違えるほど映像がキレイになることはあまり知られていません。この連載ではその効果と種類を、イマドキのトレンドも踏まえて紹介します。
ここで紹介するスクリーンの「機構」。左から「掛け図式」「巻き上げ式」「フレーム式」「立ち上げ式」

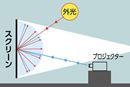

連載の第2回では、スクリーンの「幕面」自体について解説しました。
この第3回では、部屋への設置方法や使い方そのものを大きく左右する「機構」の違いについて説明します。「幕面」と幕面を支えるメカニカルな部分、この2つの掛け合わせで製品の価格が決まります。テレビで言えば液晶や有機ELなどの画面部分とフレームや脚部などとの関係と同じです。
最もシンプルでお値打ちなのが、2本の棒で上下を留めただけの「掛け図式」です。いわゆるタペストリーのようなもので、使わないときは巻き取っておき、使うときは広げて壁に掛けることを想定しています。
シンプルで安価なのが「掛け図式」。巻物のような形で壁に掛けて使うのが基本ですが、スタンドが用意されている場合もあります。下記サンワサプライなど、どちらかと言えばオフィス用品としてのたたずまいです
プロジェクター同様、「普段はしまっておいて見るときだけ出すのならこれでもいい」と思うかもしれませんが、連載の1回目で説明したとおり、スクリーン最大の敵は「巻きじわ」です。特に立てて(縦に)保管することは厳禁なので、80インチでも長さが1800mmほどにもなる巻物を横置きする収納場所を考えると、実は価格以外のメリットはほとんどないのです。
そこで、大きな巻物はあらかじめ壁ないし天井に取り付けておき、使うとき引き出そうということになります。これが、「巻き上げ式」です。これには、コストパフォーマンスにすぐれた「手動式」と、リモコン(または壁スイッチ)で上下する「電動式」があります。
ロールスクリーンと似た構造の「手動巻き上げ式」スクリーン。「電動式」よりも安く購入できますが、利便性と実用性にも差が出ます
「べつに、カッコよく電動でガーッと上下しなくてもいいや」と思いがちですが、実は電動にすることは、「カッコイイ」こと以上に重要なメリットがあります。ここでも「巻きじわ」が直接関係してきます。
「手動巻き上げ式」スクリーンは巨大な幕面を収納するために、本体に強力なバネを仕込んで巻き上げ収納しています。そして使うときは、その力に逆らって一気に引き下ろすことになります。こうして使うたびに手動で下のバーの中心をグッと引き下げる……そういったことを繰り返していくと、スクリーンには「V字」のしわが生じてしまうのです。
第1回で説明したとおり、幕面にはしわが生じにくいような裏面加工がされていますし、下のバーにも多少のしわならあとからでも調整できるダイヤルが内蔵されていたりするものですが、それでは解消できないしわが強まっていくのは事実。ちょっと神経質な人には気になることでしょう。
「手動巻き上げ式」では製品選びの幅が広がります。「掛け図式」同様にサンワサプライなどのオフィス用品然とした製品もあるいっぽう、キクチなどホームシアター向け製品も視野に入ります。
この点、「電動巻き上げ式」を選択すると、引き下げることの繰り返しで生じる「V字」のしわ問題が解消されます。
「電動巻き上げ式」はケースにモーターが入っていて、スクリーンの昇降をリモコンで操作できます。ケースの近くに電源が必要になることにも注意しましょう
また、最近では電動モーターの性能が進化して小型・静音化、低価格化しており、「手動巻き上げ式」よりちょっと価格は上がりますが「電動巻き上げ式」も身近な存在になってきています。安価な製品を探しているならば、エリートスクリーンやキクチの「グランヴュー」シリーズなどがぴったりです。
実は、「ホームシアター」を紹介する雑誌などに掲載されている、リビングでのホームシアターを実践しているお宅の大半は、この「電動巻き上げ式」のスクリーンをテレビの前に天井付けしています。それは、普段の“ながら見”はテレビで、来客時やアフターディナーの「プライムタイム」ではスクリーンを下ろし家族で大画面を楽しむ、いわゆる「2ウェイ」シアターのスタイルを取っているからです。
三重県のU邸の例。2人のお子さんの健康を思いやり天然素材で組み上げたリビングには、普段使いのテレビと映画鑑賞のための電動巻き上げ式スクリーンが併設されています(インストーラーは四日市無線の樋口さん) (C) hiro_c
このように「電動巻き上げ式」であれば「V字」のしわは生じることなく、下のバーがオモリとなって巻きじわは生じにくいのですが、それでも上げ下げを繰り返すと、今度は左右に内巻のカールが生じることがあります。
そこも気になるというこだわりユーザーには、横方向にもワイヤーでテンションを掛ける「タブテンション」というタイプもあります。平面性がより強く要求される超短焦点プロジェクターにも好適です。
「タブテンション」(サイドテンションとも呼ばれる)機構を持った「電動巻き上げ式」スクリーン
スクリーン脇に黒いマスクがない、アスペクトフリータイプもあります
「タブテンション」機構は画質にこだわる人向けのため、高価になりがち。上記オーエスの幕面はブランド最高峰のマット系「ピュアマットIII Cinema」、エリートスクリーンはやはりブランド最高峰のマット系「シネホワイト」を採用しています。
いっぽう、テレビとの「2ウェイ」は行わず、すべてプロジェクター&スクリーンだけでいいという生活スタイルもあるでしょう。ひとりで部屋を独占できる場合はもちろん、部屋に大きな黒い板(テレビ)は置きたくない!というインテリア志向の方々からよくそうした声が聞こえてきます。
また近年、ランプ交換がほぼ必要ないレーザー光源のプロジェクターや、3000、4000ルーメンといった明るいプロジェクターの登場により、ちょっとした工夫でテレビとそん色ない使い勝手が可能になったという背景も要因のひとつでしょう。
「2ウェイ」を辞める……すなわち、スクリーンを巻き上げる必要がなくなると、スクリーンの最大の敵「巻きじわ」から開放される「フレーム式」が最も有利です。
ここで言う「フレーム式」とは金属などのフレームにスクリーン幕面を固定し、壁面に「張り込む」製品のこと。幕面周辺にまんべんなくテンションをかけるので、最も平面性が確保しやすい方式です。つまり画質を優先するならば「フレーム式」ということです
「フレーム式」も「掛け図式」と同じように壁に掛けるのですが、タペストリーのようにヒラヒラとぶら下げるのではなく、アルミなどの強固なフレームに直接テンションを掛けて幕面を留め付けるので、画面は常にフラットです。
また、巻き上げタイプのように、不意に小さな虫などを巻き込んで「幕面」を汚してしまうといった“事故”も防げます。
ちなみに、スクリーンの幕面をゴシゴシ拭くメンテナンスは厳禁。第2回で説明したとおり高級スクリーンの表面は繊細な構造をしていますので、刷毛などでほこりを払う程度にしましょう。
肝心の価格ですが、一時期ほど「電動巻き上げ式」との差はなくなってきました。考えてみれば、モーターは低価格化する一方、鉄骨資材の価格が上がっており、「電動」=高級、「フレーム」=安物という時代は終わっています。画質最優先かどうか、「2ウェイ」シアターにするかしないか、といった基準で選択すればよいと思います。
ここまではスクリーン「機構」の基本3パターン、「掛け図式」「巻き上げ式(手動・電動)」「フレーム式」について説明してきました。
しかしこれはいずれも、壁や天井に固定する必要があるものばかり。特に「巻き上げ式」は、壁や天井に補強が必要な場合もあります。そうなると全国各地のホームシアター作りの専門家である「インストーラー」に依頼したり、工務店に頼んだりして、工事をすることになります。
加えて、「賃貸で壁に穴を開けられないんだけど」というユーザーもいるでしょう。
そこで、プロジェクターのモバイル化とともに最近再び注目を浴びているのが、モバイルスクリーンです。
これらは、吊り下げるのではなく、床に置いて引き上げる構造のもの。その意味では「巻き上げ式」の逆パターンで「引き上げ式」とでも呼ぶべきものなのでしょう。ただ、一般的には「立ち上げ式」と呼ばれています。
このタイプは、「巻き上げ式」のように幕面下のバーをオモリにしてテンションを掛けることができないので、工夫が必要です。
たとえば、後ろにカメラの一脚のように伸縮するつっかえ棒を立てて引き上げるタイプや、ガス圧のパンタグラフで好みの場所で止められるタイプなどがあります。
背面のつっかえ棒で固定する「立ち上げ式」スクリーンの例。安価な製品に多いタイプで、少し手間がかかります
こちらがパンタグラフタイプの例。利便性を考えるならば断然こちら。スクリーンを引き上げるだけで任意の位置で止まってくれます。下記、オーエスの定番マット系幕面「ホワイトマット」を採用した製品などは、比較的安価に購入できます
そして「巻き上げ式」と同様に「立ち上げ式」にも、左右にもテンションをかけてカールを防ぐ「タブテンション」タイプがあります。
これら「立ち上げ式」はモバイルスクリーンとはいえ100インチともなれば結構な重量があります。また、モバイルスクリーンに限ったことではありませんが、平屋1階以外では、マンションなどのエレベーターに載るか、階段を回るか、玄関の間口を通るかなども事前に確認が必要です。商品の配送においても、通常の宅配便とは異なる「長尺物」の扱いになりますので、注文時にチェックしましょう。その意味では家具と同じで、現場で組み立てる(ノックダウン)の「フレーム式」は、マンション設置でも融通がききます。
将来新築やリノベーション住宅でリビングシアターを楽しみたいけど、今は賃貸なので……というアナタ。「立ち上げ式」でも、「巻き上げ式」と基本的な仕組みは同じなので、まずはそこからチャレンジしてみることもアリです。いっぽう、「フレーム式」を買っておくと、将来新居に引っ越しても大工さんに壁を補強してもらえば自分で壁掛けできるなど、比較的長く使えます。
スクリーンはヘビースモーカーや焼き肉パーティー好きでもなければそれほど黄ばんだり汚れたりは気にならず、一度買うと意外と買い換えないものです。ぜひよいものを手に入れましょう。


















![LAVIE Tab T12N T1275/LAS PC-T1275LAS [クラウドグレー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001767444.jpg)



![TW-DV7A [ホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001764902.jpg)