国内正式ローンチから半年で軌道に乗ってきた、ハイレゾも再生できる音楽ストリーミングサービスQobuz(コバズ)。新しもの好きマニアならずとも、そろそろ「やってみたい」と思い始めた音楽ファンは多いはず。そこで「イマドキのQobuz界隈」をまとめてみました。再生方法から、高コスパの本命製品を取り上げ、その使い勝手と音の印象を実機レビュー!
2024年10月に日本に上陸した音楽配信サービスQobuz。2007年にスタートしたフランスの音楽聴き放題サブスクリプションサービスで、オーディオ愛好家でも満足できる音質を備え、再生できる楽曲は1億曲以上とされています。
サービス名の由来は、主にカザフスタンで生まれた古代の象徴的で神聖な楽器「Kobyz」とのこと。超自然で不思議な力を備えるサービスを目指しているということなのでしょう。そんなQobuzの四大特徴は、「高音質」「音楽好き集団による高度なキュレーション」「ダウンロードあり」「オーディオシステムとの統合」と言えます。
何といっても最大の長所は、高音質デジタル配信であること。さまざまなサンプリングレートで提供されており、サンプリングレート192kHzや96kHzといったハイレゾリューション(ハイレゾ)のものもあれば、44.1kHzのCDクオリティー(ロスレス)もあります。個人的な見解ですが、いずれも無理にアップコンバートされたものではなく、元々のデータが素のまま流れてくる印象で、好感が持てます。
もう1つの大きな特徴は、アナログなキュレーション。「アナタガ ヨクキクモノカラ AIガ アナタノタメニ エラビヌキマシタ……」ではなく、音楽好きな世界のQobuzスタッフが、音楽的な立場で、中立かつすぐれたライブラリーを超アナログに作成しているんです。4月には新機能「レーベルページ」と「アワードページ」を追加。レコードレーベルやアワード受賞作品の専用ページを通じ、選りすぐりのセットリスト提供を受けられるというわけです。
これと関連しているのが、読み応えのあるQobuzマガジンの存在です。これも音楽好きなQobuzのスタッフが編集・作成しており、日本でのサービス母体となった前身e-onkyo music時代の貴重な読み物も掲載されています。
オフィシャルのアプリを使うと、さまざまな音楽との出会いを提案してくれます
さらに1億曲以上の音楽ファイルダウンロード販売があるのもうれしいポイント。大好きな音源が、物理メディアなしでも、DSDも含む「音楽ファイル」という形で手元に保存できます。
そんなQobuzですが、本格的なオーディオ機器で再生しやすいのも特徴のひとつ。Qobuz再生に対応したオーディオ機器(プレーヤー/ストリーマー)を1つ追加すれば、PCレスで全世界の1億曲がすぐさま楽しめます。
Qobuzと提携しているメーカーはオフィシャルサイトに掲載されているのですが、あくまでメーカー名が並んでいるだけ。実際にQobuz再生に対応した機器はどれなのか? 日本で流通している製品の中から価格.comマガジン読者に“刺さりそう”な高コスパモデルを紹介することが本稿の趣旨です。
ここで注目してほしいのは、ロゴ右肩に「Qobuz Connect」とあるブランド。「Qobuz Connect」機能に対応した製品であれば、「Qobuz」アプリで選んだ楽曲を直接オーディオ機器で再生できます。スマートフォン(「Qobuz」アプリ)で快適に選んだ楽曲をそのまま高音質で再生できるわけで、「Qobuz Connect」対応であれば、より高い利便性が期待できるということです。
本稿で紹介する製品では、WiiMの製品が「Qobuz Connect」対応です。
なお、Qobuzはお試し期間として最初の1か月は無料で利用できます。また、Qobuz対応製品を扱うメーカー/ブランドは、製品購入特典としてそれ以上の無料トライアル期間をサービスしている場合があります。
「Qobuz Connect」は「Qobuz」アプリで選んだ楽曲を、対応ネットワークオーディオプレーヤーが”直接”再生する機能。Bluetoothなどの圧縮がないため、高音質を期待できます。操作は簡単で、左画面から再生先と楽曲を選ぶだけ。非常にスムーズです
そもそも、ネットワークオーディオ自体に親しみが薄いという方には、Qobuzを高音質で再生するための前提として注意点があります。それは、スマホでQobuzを再生した場合、高音質での配信を生かせない可能性があること。以下のような接続がその例です。
スマホやタブレットをプレーヤーにする、最も簡単なQobuz再生方法はこちら。特別な機器は不要ですが、せっかくのハイレゾ音源もスマホでBluetooth接続のためにデータを変換・圧縮してしまうため、Qobuzの高音質メリットを最大限生かせません。これはコーデックを問わず言えることです
スマホやタブレット用に提供されている「Qobuz」アプリは、基本的にあくまでスマホ/タブレット類そのものをプレーヤーとして再生するためのものです。この場合、そのプレーヤー(スマホなど)自体が音源をインターネット経由で受信し、Bluetoothなどで接続した外部ヘッドホンやスピーカー類に音楽信号を送ることになります。
Qobuz対応ネットワークオーディオプレーヤーがインターネットから音源を直接取得して再生する例。すでにアンプやスピーカーを持っている方ならば、システムにプレーヤーを足せばよいだけです。スマホ/タブレットはあくまでリモコンの役割
それに対して本稿で説明・試聴するのは、ネットワークオーディオプレーヤーがインターネット経由で高音質音源を受信し、再生する方法です(有線LAN接続推奨)。スマホ/タブレット類は、音源自体のやり取りをしません。あくまでネットワークオーディオプレーヤーを操作するためだけに使うので、Wi-Fiリモコンのような役割を果たします。これは、「Qobuz Connect」での再生でも同じ。
この方法のよいところは、高音質と利便性を両立できること。スマホやPCでの再生で高音質を目指す道もありますが、簡単に、しかも便利で高音質なシステムを構築できる方法として、Qobuz対応ネットワークオーディオプレーヤーを紹介します。
今回2025年3月から4月にかけて行った取材では、リモコンとして「iPhone 15」を使い、App Storeから各プレーヤー専用アプリをダウンロードして操作し、筆者宅のオーディオ機器で再生しています。「Qobuz Connect」で同様の操作が可能になったものについては機会があればリポートしたいと思います。
では、Qobuzスタートアップにふさわしい高コスパ機器をブランド別に紹介していきます。ここで触れるするのは、WiiM、Bluesound、Sonos、アイ・オー・データ機器の「Soundgenic Plus」、ARCAM、ヤマハ、デノン、マランツという8ブランドです。
・約2万円でアドオンできる「WiiM Pro」
・DACに「AKM 4493SEQ」搭載の上位機「WiiM Pro Plus」
・タッチパネルやHDMIなどを装備した最上位機「WiiM Ultra」
・HDMI搭載プリメインアンプ「WiiM Amp」
・プリメインアンプの上位モデル「WiiM Amp Pro」
まず紹介するのは、WiiM(ウィーム)。WiiMはアメリカで2014年に設立されたブランドで、これまでもHarman、JBL、ヤマハなどのスマート製品向けにワイヤレス技術を提供してきました。なお、Amazonで扱われている商品は直輸入品扱い。日本の輸入代理店(エミライ)のサポート外ということに注意しましょう。
操作は、WiiM製品専用アプリ「WiiM Home」で行います。後述するSonosやBluesoundと同様に、1つのアプリ上で、複数の部屋で異なる曲、あるいは一斉に同じ曲を再生する「マルチルームオーディオ」も可能です。
なお、WiiMは、同社オリジナルアプリ以外に、「Qobuz Connect」にも対応しています。
WiiMにはネットワークオーディオプレーヤーとプリメインアンプがありますが、ここで取り上げるのはプレーヤーの「WiiM Pro」です
今回お預かりしたのは現行品の中で最も安価な「WiiM Pro」。「WiiM Home」アプリをダウンロードして起動すると、ネットワーク上に登録対象のモデルがすぐさま表示され、ガイドに沿って簡単に設定を完了できました。
リアパネルにはアナログとデジタル両方の音声出力が用意されます。電源供給はUSB Type-C端子から行うタイプ
左が専用アプリでレイテンシーを測定しているところ。マルチルームで同じ曲を再生する際の音の同期を図っているようです。右は2部屋で別の曲を流している際の画面。マルチルーム設定も簡単です
左の画面で音声出力端子を選択。また、Apple Homeとの連携も簡単です。音楽再生画面の下にデバイスの設置場所と出力が表示されました。ファイルフォーマット、ビットレートまで表示されています
付属のRCAラインケーブルはやや心許なく、むしろケーブル交換によってダイレクトに変わる潔さを褒めてあげましょう。お手元にあるケーブルをあれこれ使いこなしてみると、約2万円とは思えないハイファイ音質です。もっとも、デジタル出力があるので、お気に入りの外部DACがあればそれを活用するとなおよし。「とにかく低コストでちゃんとQobuzを試したい」という場合の筆頭間違いナシです。
「WiiM Pro」本体と同価格帯のRCAケーブル サエク「SL-1980」をつなぐと音色は変わらないものの、クリアーかつ中低音が芳醇に響きボーカルの肉付きがよすぎる印象でした。数千円程度の一般的なOFCケーブルあたりがバランス良好かもしれません
「WiiM Pro」の上位モデル「WiiM Pro Plus」(左)と「WiiM Ultra」(右)
なお、別の機会に上位モデル「WiiM Pro Plus」「WiiM Ultra」も試聴しました。「WiiM Pro Plus」のアナログ出力は「WiiM Pro」より高品位。個人的には、さらにもうちょっと頑張って(価格の高い)なんでもアリの「WiiM Ultra」を推したいと思いました。大きなカラーディスプレイがあり、接続端子にはARC対応のHDMIからアナログレコード用のフォノ入力まで揃えます。音質的にも「WiiM Pro Plus」よりさらに一枚上手で、接続ケーブルを高級品に変えても大げさになることなく上品な方向に化ける本格派です。
・エントリークラスのプレーヤー「NODE NANO」
・HDMI搭載のプリメインアンプ「POWERNODE EDGE」
Bluesound(ブルーサウンド)は、1978年にカナダで創設された企業をルーツとするブランド。現在ではNADやPSBといったオーディオブランド(グループ企業)と技術や理念を共有し、商用のマルチルームオーディオでも人気を博しています。輸入代理店は(株)PDN。
本体の操作は、専用アプリ「BluOS Controller」で行います。WiiM同様、マルチルームオーディオが可能で、Amazon Musicなども含めて1つのアプリ上で複数の部屋の異なる曲の再生、同じ曲の一斉再生も指示できます。
「NODE NANO」のフロントフェイスはタッチパネルになっていて、簡単な操作が可能。ランプが点灯します
今回お預かりしたのは、最もシンプルで売れ筋のネットワークオーディオプレーヤー「NODE NANO」。サイズ感や入出力端子は「WiiM Pro」とほぼ同じながら重量は0.57kgと倍近くあり、手に持ってみると底板に重量感があります。
アナログ(RCA)とデジタル(同軸、光)音声出力を持ったシンプルなリアパネル
WiiM同様マルチルームオーディオが可能なので、1台ずつ場所の名前を付けられるのが便利。右は音楽ストリーミングのサービス一覧。もちろんQobuzを選択します
わかりやすくむだのないインターフェイス。音量調整は画面下のスライド操作で。「FLAC 24/192」といったスペックもきちんと表示されました。右画面のように、シンプルなトーンコントロール(イコライジング)もできます
専用の再生アプリ「BluOS Controller」は、表示がシンプルで操作も明快。再生ファイルの表記が出るので、ハイサンプリングレートのスペックを求める人にとっては安心でうれしい機能です。
肝心のサウンドは、オーケストラが静かで音の消え際や倍音まで豊か。対抗馬の「WiiM Pro」や「WiiM Pro Plus」はメインとなるボーカルや楽器が前に張り出してくるイメージなのに対し、「NODE NANO」は奥行き方向に音場が広がるイメージ。また、ケーブルをアップグレードすると、派手になることなく、品位が上がります。“キンシャリ”になりがちなポップスも下品にならず、これで6万円弱という価格はたいしたものです。
入出力端子などの仕様だけを比較すると、WiiMのラインアップよりも全体的に高価ですが、音質的には同価格帯の「WiiM Ultra」クラスと同等という印象でした。
・シンプルなネットワークオーディオプレーヤー「Sonos Port」
・HDMIも搭載するプリメインアンプ「Sonos Amp」
・14スピーカーの本格派サウンドバー「Sonos Arc Ultra」
・5スピーカーのコンパクトサウンドバー「Sonos Beam (Gen2)」
「Sonos Arc Ultra」
Sonos製品は共通の専用アプリ「Sonos」で操作します。スマートフォンと本体がすんなり連携し、手慣れたもので動作はきわめてスムーズ。このスムーズさ、アプリの出来のよさは図抜けていると言えます。
Qobuzのみならずインターネットラジオ(Sonos Radio)やApple Musicも一括で操作でき、サービスをまたいだ検索も簡単です。Qobuzでファイルフォーマットの表示はありませんが、Apple Musicでは対応コンテンツでDolby Atmos表示がされました
「Sonos Arc Ultra」の詳細なインプレッションや使いこなしは別記事をご参照いただきたいのですが、「Trueplay」による自動音場補正を施した後のサウンドは、華やかな高音域と、アクティブスピーカーらしいマッシブな低音域が印象的。クラシックはやや煌びやかかつまろやかで上品な鳴り方で、最新の“キンシャリ”したポップスでも耳に付く尖ったところを上手に抑え、マイルドに再生します。先鋭感あるハイファイサウンドを好むオーディオマニアよりも、広く音楽愛好家が日常的に聴くのに向いていると感じました。
発売から少し経過していますが、ネットワークオーディオプレーヤー「Sonos Port」、プリメインアンプ「Sonos Amp」もラインアップしています。きわめてスムーズな使い勝手は同じなのでぜひ候補に検討してみてください。
「Soundgenic Plus」にはHDDとSSDモデルがあり、価格が異なります
・2TBのHDDを内蔵する「HDL-RA2H」
・1TBのSSDを内蔵する「HDL-RA1S」
ちょっと変わり種ながら少ない出費でQobuz再生に対応する裏技的存在として、「Soundgenic Plus」を紹介します。本来は、音楽ファイルを保存しておくためのNASですが、Qobuz、Amazon Music再生のプレーヤー(ストリーマー)としての機能もまかなえるすぐれものです。
「Soundgenic Plus」の使い方は、Qobuz対応ネットワークオーディオプレーヤーと同じ。音楽ファイルを保存するためのストレージ(NAS)でありながら、プレーヤーにもなります。音量調整もできるため、アクティブ(アンプ内蔵)スピーカーに直結してもOK
プレーヤーになると言っても、RCAなどの音声出力端子はありません。USB端子と、付属する特殊なケーブルを利用することでアナログ音声出力が可能になります
こちらがアナログ音声出力のための専用ケーブル。USB DAC機能を持っているということでしょう
今回お預かりしたのは、「HDL-RA2H」という型番(2TBのHDD内蔵モデル)の「Soundgenic Plus」。いわば音楽再生に特化したNASないしミニPCのようなものと言えます。
注意点は、Wi-Fi接続に対応していないこと。有線でLANにつなげば問題ないのですが、スマホやタブレットをリモコンとして使うため、Wi-Fi環境は必須です。
操作は「fidata Music App」で行います。このアプリでは、PCを介することなくCDをリッピング(NASに保存)したり、ダウンロード(購入)した音楽ファイルを再生したりできます。従来型ネットワークオーディオの延長線上にあるインターフェイスと言えるでしょう。LAN上にあるお気に入りの音楽ファイルをプレイリストに追加し、順次再生するというスタイルが基本だとわかります。LINNがNASに格納された音源の再生を中心にしていた時期の「Kinsky」というアプリに似ています。
宅内の音楽ファイル再生をベースにしつつ、インターネット経由でのストリーミング再生機能を足したような製品となっているのです。
ストリーミング再生する場合には、「Soundgenic Plus」をストリーマー(プレーヤー、レンダラー)として使うことになります。それが、従来型ネットワーク再生アプリからみると、ちょっと“裏技的”と書いた理由です。
音楽再生機として「Soundgenic Plus」を選ぶと、「USB Audio」と右側に「Streamer」の表記が表れました。そのうえで「Music Services」から「Qobuz」を登録して選択。これでQobuzを再生できます
肝心の使い勝手ですが、ソフト自体が軽いのでしょう、Qobuzでのサムネイル表示、検索はなかなか速くパラパラと出てきて快適。
サウンドとしては、線が細めでスケール感も控えめの締まったサウンド。ソース以上に高音域が”キンシャリ”したり中低音が張り出したりといったあざとさがまったくなく、フラットかつ素直に出してくるのは好印象です。
専用のケーブルを使った非常に簡単な接続方法ですが、イエス「Roundabout」などはブリブリとした押し出しこそないもののギターが下品にならず響きが魅力的。諏訪内晶子のバイオリオンも艶やかでした。同価格帯のCDプレーヤーを買い直すぐらいなら本機で楽しんだほうが断然よいと思わせる実直な作りでした。
なお、本来的な使い方として一般的なUSBケーブルを使ったUSB DAC接続もできます。この構成であれば、より好みのサウンドを目指しやすいでしょう。
こちらがUSB DACを使う接続イメージ。「Soundgenic Plus」とUSB DACを一般的なUSBケーブルでつなぎ、デジタル音声出力を送ります
USB端子は2つあるため、1つにディスクドライブをつなぐと、CD再生も可能です。WAV,FLAC形式でのリッピング(NAS内へのデータ保存)にも対応していて、オンラインデータベース(Gracenote)からメタデータも取得してくれます。これらの動作はもちろんPCレス
NASを持っていない方、すでに持っているNASからデータを移管してシンプルに音楽を楽しみたい方、CDリッピングをPCなしで行いたい方、ストリーミングサービスはどちらかというとサブで時折Qobuzが聴ければよいという方に「Soundgenic Plus」はぴったりです。
そのほか、注目したいのは英国ブランドARCAM(アーカム)。すでに生産終了品ではありますが、Qobuz再生に対応したプリメインアンプ「Solo Uno」の価格.com最安価格(2025年5月14日時点)は28,900円(税込)。現行製品ではないため、お預かりしての試聴はできませんでしたが、非常に魅力的な価格です。
また、同社オリジナルアプリ以外に、「Qobuz Connect」にも対応しています。本国のオフィシャルページではすでに新製品が登場している様子。これらが日本市場に投入されれば、こちらも有力候補となるでしょう。
ヤマハのエントリーモデルに当たる「RX-V6A」もQobuz対応製品。右がMusic Castアプリ画面です。マルチルームオーディオ対応で、ファイルフォーマット、サンプリングレートまできっちり表示されました
ここまでは、新しくプレーヤーなどのハードウェアを追加することで高品質なQobuz対応を果たす方法を紹介してきました。
ところが、AVアンプをお持ちでしたら、実はQobuz対応しちゃってるかもしれません。ヤマハのAVアンプがその一例です。
筆者宅にもヤマハの“AVプリアンプ”「CX-A5200」がありますが、実はQobuzの再生を一度も試したことがありませんでした(苦笑)。今回さっそく使ってみましたが、使い勝手は悪くありません。もっとも、音質的には専用プレーヤーにはかなわないかな、といった印象ではありました。
また、D&Mホールディングスオリジナルのネットワークオーディオプレーヤー機能「HEOS(ヒオス)」が「Qobuz Connect」に対応しました。ということは、デノンやマランツのAVアンプも、Qobuzの高音質再生に対応したことになります。こちらにも注目しましょう。
当初は、編集担当ともども「音質云々よりも、初心者向けに、アプリの使い勝手などを重点に調査しよう」と始めた本企画。実際に各モデルをお預かりして自宅で使ってみると、なかなかどうして聴き応えが。むしろ格安モデルほどアクセサリーによる音の違いがダイレクトに反映されたりして、興味深い機会となりました。
かくいう筆者はメインとなる試聴室兼仕事場でLINNのネットワークプレーヤー「SELEKT DSM-K」、または、「MacBook Air」と「Audirvana Studio」によるPCオーディオの2本立てでQobuzを楽しんでいます。
「LINN」アプリでの操作画面。ファイルフォーマット、サンプリングレート、ビットレートまで表示されていて便利。マルチルームオーディオにも対応します
そんな私でも、「Sonos Arc Ultra」はリビングの超短焦点プロジェクターと組ませたいと思いましたし、寝室などサブルームのマルチルームオーディオ再生に向くかと思って借りたBluesoundの「NODE NANO」や「WiiM Ultra」はメインのオーディオシステムと組んでも立派なハイファイサウンドであることが確認できて本当に驚きました。
完成されたオーディオシステムをお持ちの方も、これをキッカケにいい音楽にもっとふれ合いたい方も、こうした対応機器をアドオンしてQobuzの世界に足を踏み入れてみることをおすすめします。
Wi-Fiを含む宅内のLAN環境、スマートフォンやタブレットは必須ですが、新しい音楽に触れる機会がない方ほど、Qobuzの超アナログなキュレーションやAIのおすすめを通じて、聴き逃していた名作に巡り会えることのよろこびを知ることになるでしょう。

















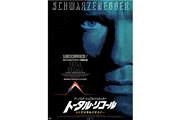

![カラリエmini TURBO ツインノズル BSK-210-W [ホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001718438.jpg)

![BRAVIA 5 K-85XR50 [85インチ]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001713719.jpg)
